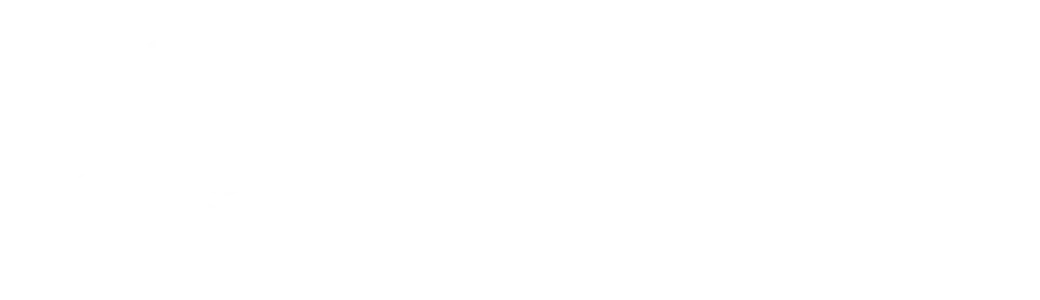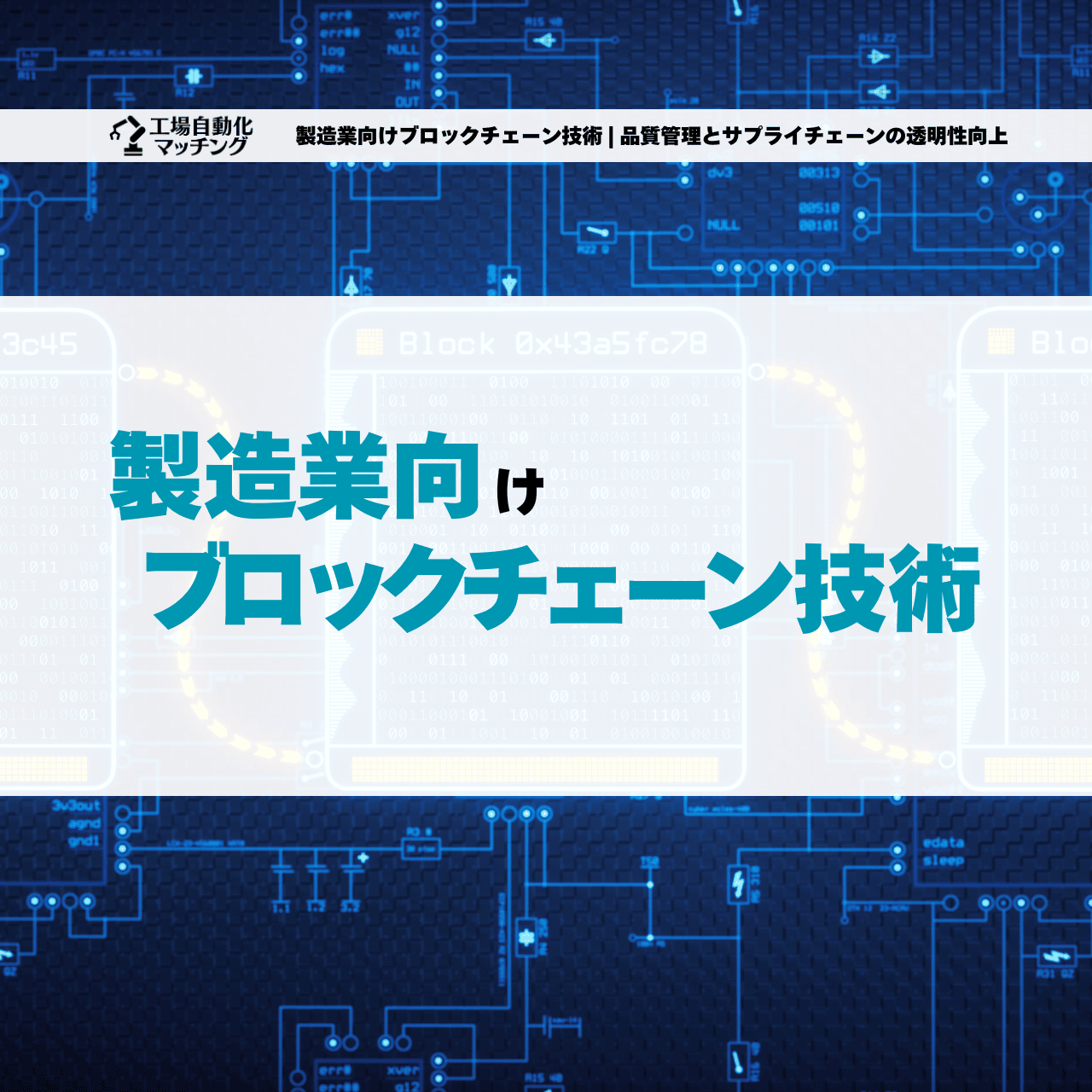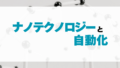品質管理とサプライチェーンの透明性向上
ブロックチェーンと聞くと、暗号資産(仮想通貨)をイメージする人が多いかもしれません。しかし近年では、製造業の現場でもブロックチェーン技術が注目されています。
特に「品質管理」や「サプライチェーンの透明性」といった分野において、データの改ざんができない、追跡性があるというブロックチェーンの特性が非常に有効であることが分かってきました。
この記事では、初心者の方でも理解しやすいように、製造業でブロックチェーンがどのように活用されているのか、どんなメリットがあるのかをわかりやすく解説していきます。
ブロックチェーンとは?
● 基本のしくみ
ブロックチェーンとは、取引履歴やデータを「ブロック」として記録し、それを「チェーン(鎖)」のようにつないでいく分散型のデータベースです。特徴は以下の通りです。
- 改ざんが極めて困難(過去の記録を書き換えられない)
- 情報が分散管理されている(特定のサーバーに依存しない)
- 履歴がすべて記録され、誰でも追跡可能
この技術を製造業の現場に応用することで、「品質トレーサビリティ」や「サプライチェーンの可視化」が実現しやすくなります。
製造業での活用ポイント
1. 品質管理の強化
製品が完成するまでには、原材料の仕入れから加工、組立、検査など、さまざまな工程を経ます。この各工程で発生するデータをブロックチェーン上に記録することで、「いつ・どこで・誰が・どのように」作業を行ったのかが明確になります。
たとえば:
- 材料ロットの入荷情報
- 検査結果のデータと担当者の記録
- 生産ラインでの温度や時間などの環境情報
これらを記録しておくことで、不良品が出た場合にも迅速な原因究明が可能となります。
2. サプライチェーンの透明性向上
製造業では、製品がエンドユーザーに届くまでに、複数の企業や国をまたいで流通することが多くあります。ここで課題となるのが、「誰がどこで何をしているか分かりにくい」という点です。
ブロックチェーンを活用すれば、各事業者が関わった工程やタイミングをすべて時系列で記録できます。
- 誰がいつ部品を供給したのか
- 輸送時の温度管理や日時の記録
- 工場の検査履歴
これにより、「製品の履歴が明確」で「責任の所在がはっきり」するので、取引先や消費者からの信頼性が向上します。
3. 偽造品・不正流通の防止
ブランド品や精密部品の製造業界では、「模造品」や「並行輸入品」など、正規ルートでない製品が出回る問題もあります。
製品ごとに唯一のデジタルID(NFTなど)を発行し、ブロックチェーンに紐づけることで、真正性を証明することができます。購入者や取引先は、IDを読み取るだけでその製品の履歴や正当性を確認できます。
実際の導入事例
◆ 日立製作所
製造工程の各データをブロックチェーンで一元管理し、部品ごとのトレーサビリティを強化。品質トラブルの初動対応時間を大幅に短縮。
◆ BMW(ドイツ)
サプライヤーからの部品供給に関するデータをブロックチェーンで管理。納品遅延や不良率の監視、そして信頼できるサプライヤー選定に役立てている。
◆ VeChain(中国)
ラグジュアリーブランドの真贋判定に使用。ブロックチェーンを使って製品の真偽と履歴をエンドユーザーがスマホで確認可能に。
メリットまとめ
| 項目 | メリット |
|---|---|
| データの信頼性 | 改ざん不可能な記録が残る |
| トレーサビリティの確保 | 工程ごとの履歴が明確になる |
| 責任の明確化 | トラブル時に原因を特定しやすい |
| 消費者からの信頼向上 | 製品の透明性を示せる |
| サプライチェーンの最適化 | データ共有がスムーズに |
導入にあたっての課題
● システム構築のコストと時間
ブロックチェーンを工場や取引先全体に展開するには、一定の初期投資とシステム改修が必要です。
● すべての工程でのデジタル化が前提
紙の記録や口頭伝達など、アナログな工程が残っているとブロックチェーンの効果を十分に活かせません。
● パートナー企業との連携
一社だけでなく、サプライチェーン全体が連携しなければ意味がないため、共通のルールやシステムの採用が必要です。
今後の展望
- 中小企業でも導入しやすいクラウド型のブロックチェーンサービスが登場
- スマートコントラクト(条件を満たすと自動で処理)との組み合わせによる自動発注・自動検査の実現
- ESGや環境配慮の観点から、製品のライフサイクル全体をブロックチェーンで管理する動きも加速中
まとめ
ブロックチェーン技術は、製造業にとって以下のような価値あるツールとなります。
- 品質を「証明」できる時代へ
- 工程を「可視化」し、信頼と効率を両立
- サプライチェーンの「透明性」で競争力強化
今後の製造業では、ブロックチェーンが「データを守る防波堤」として、そして「信頼をつなぐ橋」として重要な役割を果たすことになるでしょう。
導入の第一歩は、自社のどの工程やデータが「守るべき信頼」であるかを見極めることから始まります。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。