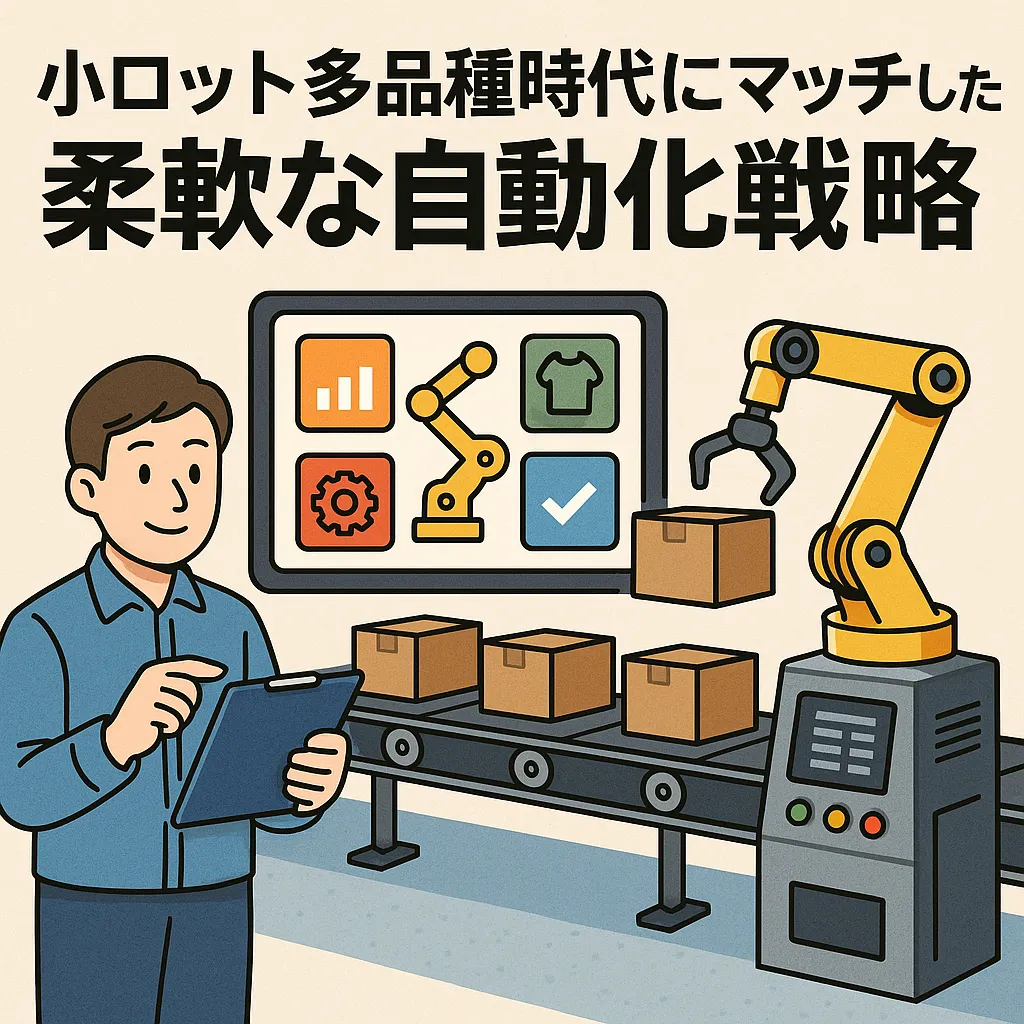かつての工場自動化といえば、大量生産・少品種のラインにおいて安定した品質と生産性を確保するためのものでした。しかし現在は「小ロット多品種」「短納期対応」「変種変量」が当たり前の時代になっています。
こうした時代において、従来型の硬直的な自動化では対応が難しく、かえって柔軟性を損なってしまうこともあります。
では、どうすれば「柔軟性」と「効率性」を両立できるのでしょうか?
本記事では、小ロット多品種生産に対応できる柔軟な自動化戦略について、初心者にもわかりやすく解説します。
なぜ今「柔軟な自動化」が必要なのか?
市場ニーズの変化により、製造業には以下のような課題が突きつけられています。
- 製品ライフサイクルの短命化
- 顧客ごとに異なるカスタマイズ要求
- 急な仕様変更や追加生産への対応
- 生産効率と品質を両立する必要性
これに対応するには、「決められたものを大量に作る自動化」ではなく、「変化に追随できる柔軟な自動化」が求められます。
柔軟な自動化戦略に必要な3つの視点
✔ 視点①:段取り替えの自動化・簡素化
小ロットでは頻繁に段取り替え(品番・金型・治具・設定など)が発生します。
対策例:
- 自動工具交換機(ATC)の導入
- RFIDタグで品番ごとに条件呼び出し
- センサ自動校正や段取り診断の自動化
→ 段取り時間が大幅に短縮され、生産切り替えがスムーズに。
✔ 視点②:モジュール化された設備の活用
工程ごとに再構築しやすいモジュール型装置やユニットを活用すると、製品の変更に柔軟に対応可能です。
例:
- モジュール式コンベア、検査ユニット
- 移動可能な卓上ロボット(協働ロボット)
→ 工程の組み換えや増設が容易になり、少量多品種への拡張が可能。
✔ 視点③:デジタル技術の活用で「設定作業」を削減
少品種多ロット時代と比べて「機械の立ち上げ作業」が多くなるため、それをデジタルで支援します。
有効な技術:
- ノーコード/ローコードで条件設定
- デジタルツインを活用した事前検証
- 作業者向けナビゲーションUI
→ 設定ミスが減り、立ち上げ時間も短縮される。
現場実践例:樹脂加工メーカー(従業員50名)
背景: 月50品目、1ロット20~100個という変動の大きい生産が主力。
課題: 品番切り替えに都度1時間以上の段取りが必要で、生産効率が上がらない。
対策:
- RFIDを使用した条件呼び出しの自動化
- 作業者の手順をタブレット表示に切り替え
- ロボットのティーチングをノーコード方式に変更
結果:
- 品番切り替え時間が60分 → 15分に短縮
- 熟練作業者に頼らない運用が可能に
- 年間の稼働率が18%向上
柔軟な自動化導入の進め方ステップ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Step 1 | 自社の「変種変量パターン」を把握 |
| Step 2 | 段取り・条件設定の時間を可視化 |
| Step 3 | モジュール化・デジタル化できる領域を検討 |
| Step 4 | 小規模ライン・工程から部分導入して検証 |
| Step 5 | 現場と連携して徐々に展開する |
よくある誤解とその解消
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 柔軟な自動化=高額投資が必要 | 協働ロボットや卓上装置は比較的安価に導入可能 |
| カスタマイズ対応は難しい | ノーコード設定やデジタルツールで対応可能 |
| 少量生産には自動化は合わない | 柔軟な運用体制なら逆に効果が出やすい |
まとめ
小ロット多品種の時代において、自動化は「固定されたライン」ではなく「変化に対応できる仕組み」へと進化しています。
現場の柔軟性を損なうことなく、自動化のメリットを最大限に活かすには、段階的で柔軟性のある戦略が不可欠です。
まずは、今の工程の中で「頻繁に変わっている場所」から、自動化導入の可能性を探ってみましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。