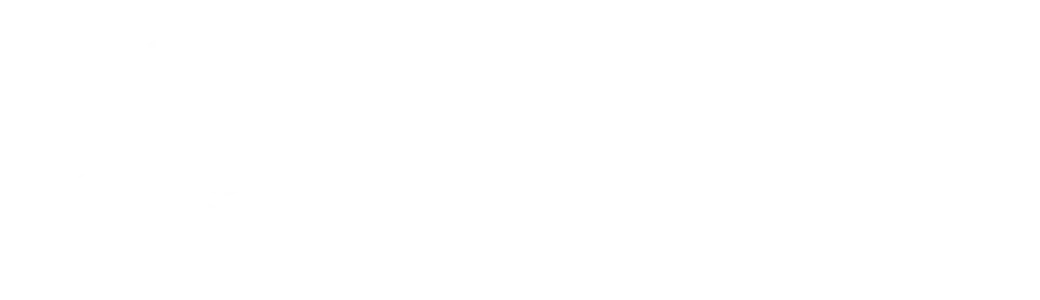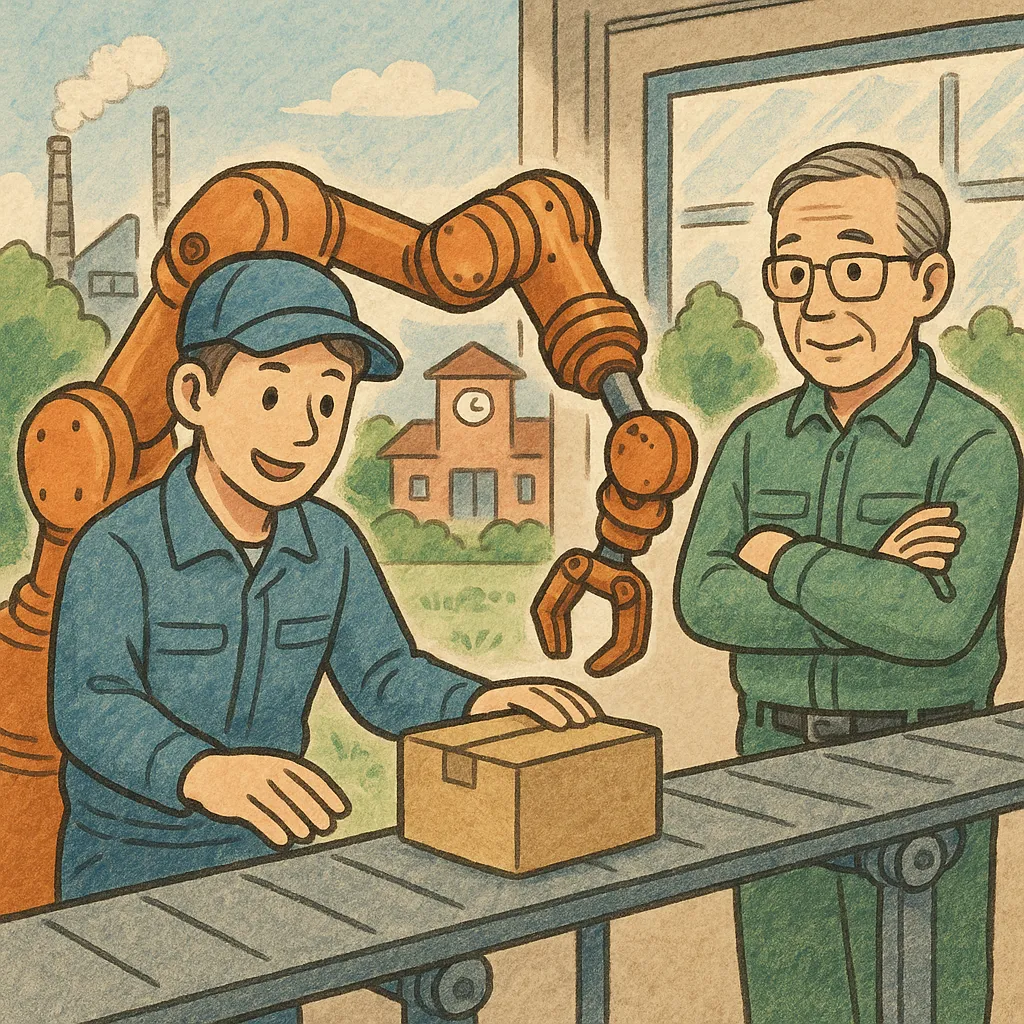製造業で自動化が進むと、「人の仕事がなくなるのでは?」という懸念の声をよく耳にします。
特に地域社会においては、「地元の雇用が失われるのでは」という不安も根強くあります。
しかし近年、自動化とローカル雇用創出を“両立”させている企業や地域が注目されています。
本記事では、その可能性と具体策をわかりやすく解説します。
自動化が「単純労働の代替」から「人と協働」へ
かつての自動化は、人が行っていた作業を「代替」するものでした。
搬送、組立、検査などの工程がロボットや自動機に置き換えられ、「人手を減らす」ことが目的でした。
しかし現在の自動化は、「人と機械が役割を分担する協働型」へと変わりつつあります。
例:
- ロボットが重い部品を運び、人が組付けを行う
- AIが検査画像を判定し、最終判断は作業者が行う
- 自動機の動作を、現場の作業者がタブレットで微調整
こうした“人の価値を活かす自動化”によって、むしろ現場の雇用が維持・発展している事例もあるのです。
地域雇用を守る3つの自動化設計思想
「人が活躍する工程」を意図的に残す
すべてを自動化するのではなく、「品質を左右する感覚的な作業」や「多品種小ロットで柔軟性が求められる工程」などを人に任せる設計を行います。
これにより、“地域でしかできないものづくり”が残ります。
地元人材を“自動化オペレーター”として育成
自動機やPLCの操作・監視・調整といった“ミドルスキル”を地域で育てれば、地元の雇用を維持できます。
現場作業者からステップアップしたい人にとっても、やりがいのある職種となります。
メンテナンス・改善を内製化して地元に仕事を戻す
導入後の保守や改良を外注せず、地域人材で担えば、継続的な雇用が生まれます。
たとえば、
- 機械修理・改造を地域の工業高校OBが担う
- 自動化改善提案を現場チームから募り、実装支援を行う
実例:自動化で雇用が“増えた”地域企業
ある地方都市の食品加工会社では、自動計量・包装ラインを導入しました。
導入当初は「人が減るのでは」と不安もありましたが、結果は逆でした。
- 減ったのは“立ちっぱなしで疲弊する単純作業”
- 増えたのは“ライン監視・品質判断・出荷管理”の仕事
- 自動化導入後に“人材教育チーム”を新設
これにより、現場の平均年齢が若返り、離職率も大きく改善しました。
地域との連携がカギになる
自動化と雇用の両立には、企業単体の努力だけでなく、「地域全体の仕組みづくり」が重要です。
- 地元の高校・専門学校と連携し、設備操作やロボット教育を行う
- 商工会や自治体が“地元自動化人材バンク”を設立
- 定年後の技術者を「自動化導入アドバイザー」として活用
こうした仕組みが、“人材を外に出さず、地域で育てて活かす”環境を整えます。
まとめ:“人を減らす自動化”から“人を活かす自動化”へ
自動化は必ずしも“雇用の敵”ではありません。
むしろ、地域に根差した“新しい働き方”を生み出すチャンスでもあります。
ポイントは以下の3つです。
- 単純作業を減らし、人の価値を活かす工程を残す
- 地元人材を“自動化人材”として育成する
- 保守・改善・運用まで地域で内製化する仕組みを作る
このように、自動化とローカル雇用は“対立関係”ではなく、“共存可能な未来”へと進化しているのです。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。