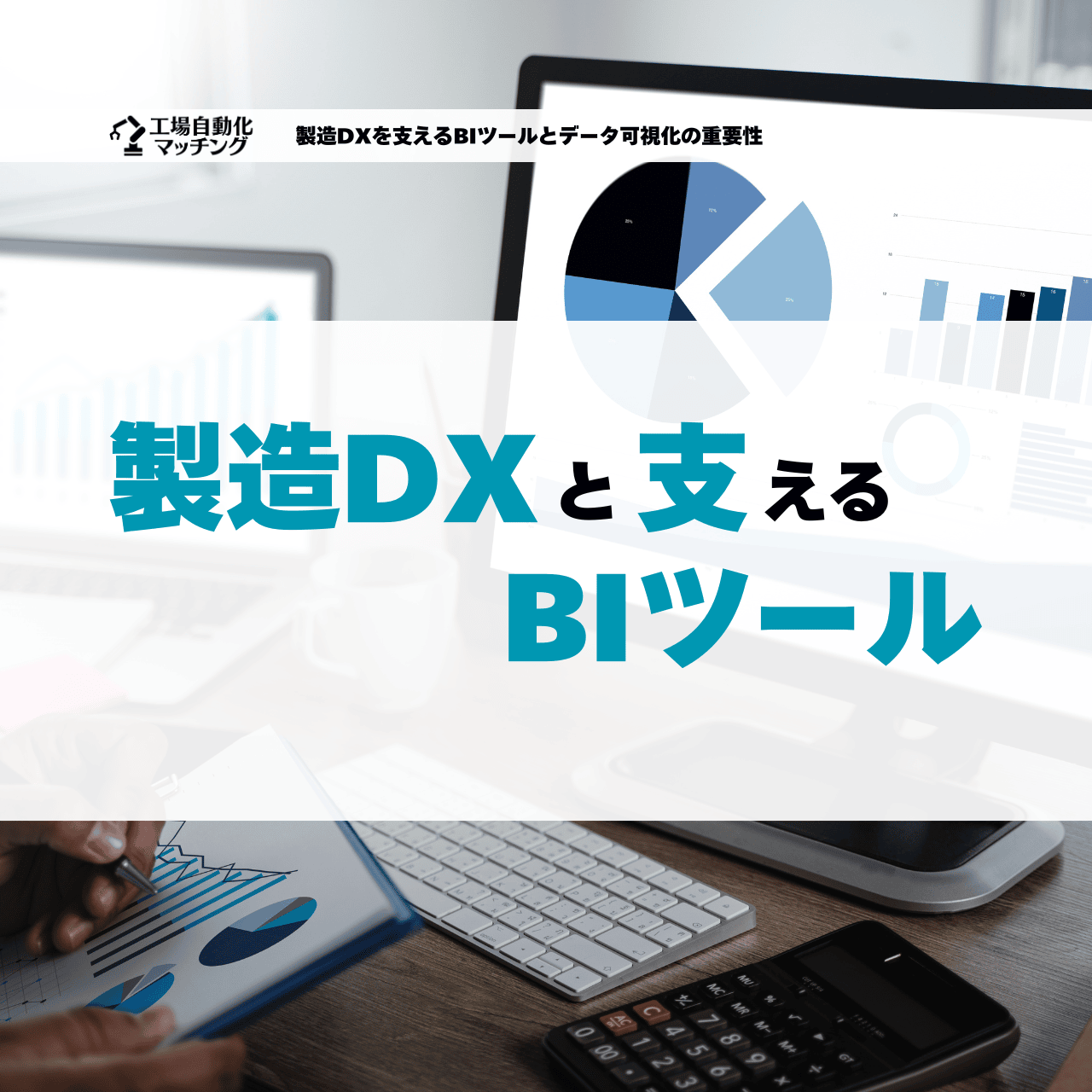製造業でも「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が定着し、工場の自動化・省人化とあわせて“データの活用”が注目されています。
中でも、蓄積された製造データを見える化し、現場の判断を支えるのが「BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)」です。
この記事では、BIツールが製造現場でどう役立つのか、なぜデータの可視化が必要なのかについて、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
そもそもBIツールとは?
BIツールとは、企業の中に蓄積された多種多様なデータを集約・分析・可視化するためのソフトウェアです。
「BI」とは「Business Intelligence(ビジネスインテリジェンス)」の略で、経営や現場の意思決定をデータで支援するという考えに基づいています。
代表的なBIツールには以下のようなものがあります:
- Microsoft Power BI
- Tableau(タブロー)
- Google Looker Studio(旧Data Studio)
- Qlik Sense
- MotionBoard(ウイングアーク) など
製造DXにおけるBIツールの役割とは?
製造業では、もともと「データを集める」仕組みは多くあります。例えば:
- 生産設備のセンサーデータ
- PLCの稼働ログ
- 作業日報や品質検査表
- 生産管理システム(MES)の実績値
しかし、これらはバラバラに存在しており、活用されずに眠っているケースがほとんどです。
BIツールはそれらを1つに集約し、次のような形で現場の“気づき”を支援してくれます。
データ可視化のメリット
● 1. 問題の「見える化」で現場改善が加速
例えば、生産ラインの稼働率をグラフで可視化すると:
- 時間帯別の稼働低下
- 曜日ごとのトラブル頻度
- 機械別の停止傾向
といった、数値では見えにくかった“傾向”や“ボトルネック”が一目で把握できるようになります。
● 2. レポート作成の工数を削減
従来のExcel集計では、毎日・毎週・毎月のレポート作成に多くの時間がかかっていました。
BIツールを活用すれば、リアルタイムでレポートが自動生成され、グラフやダッシュボードも一目瞭然。
「報告のための作業」から、「改善のための分析」へと時間をシフトできます。
● 3. 現場から経営層まで、共通の指標で判断
製造現場と経営層では、見る視点が異なります。
- 現場は「日ごとの稼働率・不良率」
- 経営層は「月次でのコスト推移や納期遵守率」
BIツールを使えば、利用者ごとに最適な可視化画面を作ることができ、組織全体で同じ数字を根拠に意思決定できる環境をつくれます。
導入時に気をつけたいポイント
● 1. データが整理されていないと活かせない
BIツールは「魔法の道具」ではありません。
活用するには、まずデータの種類や形式を整理する作業が必要です。
- センサーデータ → 時系列で記録
- 人の記録 → 日報やフォーム入力で標準化
- システム間連携 → APIやCSV出力の整備
● 2. “使い手”が理解できる設計にする
高度なグラフでも、現場の人が理解できなければ意味がありません。
「誰が見るのか」「どの判断を支援するのか」を明確にして、必要最低限から始めることが成功の鍵です。
● 3. 小さく始めて、段階的に展開
いきなり全社展開ではなく、まずは1ライン・1部署から試行導入し、効果を確認してから広げる方法が現実的です。
最初のテーマ例:
- 生産設備の停止時間の可視化
- 不良品の発生原因と傾向分析
- 段取り時間のばらつき分析
導入事例:中小部品メーカーでのBI活用
背景:手作業中心の現場で、生産日報をExcelで管理。改善活動が進まなかった。
取り組み:
- 作業記録をGoogleフォームで入力 → Googleスプレッドシートに集約
- Google Looker Studioで日別生産数・不良率・作業時間を自動集計
- 現場と管理者で「どのラインで問題が起きているか」を毎朝確認
成果:
- 手集計の手間が月10時間削減
- 不良率の高い時間帯を特定し、照明や作業手順を改善
- 作業者からの「現場が見えるようになった」という声が増加
今後の展望:AIとの連携でさらに進化するデータ活用
BIツールに蓄積されたデータは、将来的にはAIと連携し、「自動で異常検知」「予測メンテナンス」「在庫最適化」など判断そのものの自動化にもつながっていきます。
つまり、BIツールは単なるレポート作成ツールではなく、“データドリブン経営”の第一歩を担う存在なのです。
まとめ
製造DXを進める上で、BIツールによるデータ可視化は避けて通れません。
現場で起きていることを「数字で理解し、可視化し、すぐに行動できる」ようにすることが、改善サイクルのスピードを高め、生産性を飛躍的に向上させます。
まずは小さく始めて、少しずつ「現場が見える化する」喜びを実感していきましょう。それが、スマートファクトリーへの確かな第一歩となります。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。