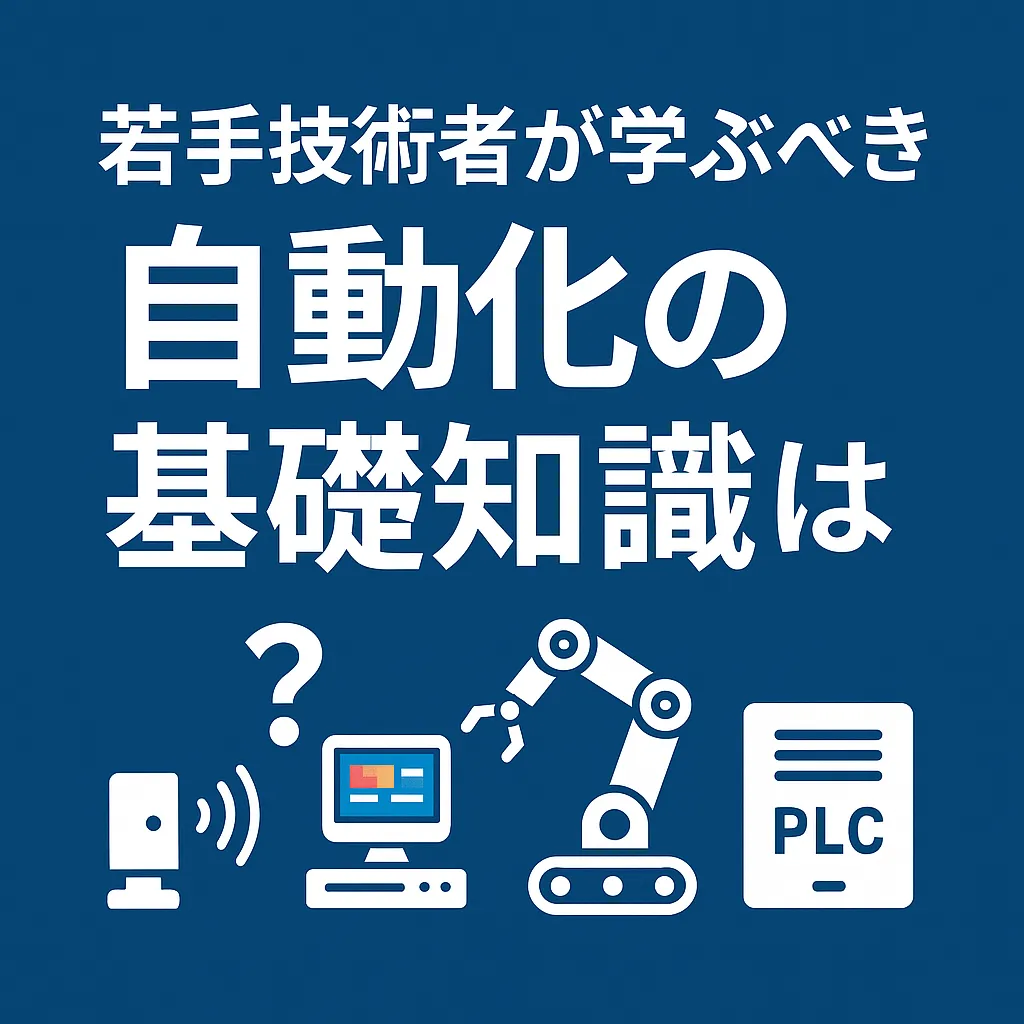近年、製造業の現場では人手不足や生産効率の向上を背景に、工場自動化(FA:Factory Automation)のニーズが急速に高まっています。
そんな中で求められているのが、現場と技術の両面を理解し、設備の導入・運用・改善に関われる若手技術者の存在です。
この記事では、初心者の若手技術者が「これだけは知っておくべき!」という自動化の基礎知識や概念を、わかりやすく解説します。
1. 自動化とは?
製造現場における「自動化」とは、人が行っていた作業を機械やロボット、ソフトウェアで代替・支援する仕組みのことです。
以下の3段階に分けて理解するのが基本です。
● レベル1:機械化
人が操作するが、作業の一部(搬送、穴あけ、切断など)を機械が代行
● レベル2:自動化
一定の手順で、人が関与せずに自動で動作する装置やロボット
● レベル3:知能化(スマート化)
センサーやAIが状況を判断し、自律的に動作や制御を最適化するシステム
2. 自動化の目的とメリット
単に「人件費を減らす」ことだけが目的ではありません。以下のような多面的なメリットが期待されます。
- 品質の安定化:人の熟練度によらず、同じ精度で作業が可能
- 生産性向上:24時間連続運転・高速化が可能
- 安全性向上:危険作業をロボットに任せられる
- トレーサビリティ:作業履歴や不良の原因分析が可能に
- 人手不足対策:少人数でもラインを維持できる
3. 若手が理解すべき自動化システムの構成要素
自動化システムは、以下のような要素の組み合わせで構成されています。
● ① センサー
物体の有無、距離、温度、圧力、色などを検知する装置
例:光電センサー、近接センサー、カメラ(画像処理)
● ② アクチュエータ(駆動系)
実際に「動く」部品
例:モーター、エアシリンダー、ロボットアーム
● ③ コントローラー(制御装置)
入力に基づいて出力を制御する「頭脳」部分
例:PLC(シーケンサ)、マイコン、PCベース制御
● ④ HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)
操作画面、モニターなど、人が機械とやり取りする部分
例:タッチパネル、スイッチパネル、表示灯
● ⑤ 通信ネットワーク
設備間で情報をやり取りする仕組み
例:Ethernet/IP、CC-Link、Profinet
4. よく使われる自動化技術用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| PLC(シーケンサ) | 入出力信号を制御する装置。自動化の中枢。 |
| タクトタイム | 1つの製品を作るのにかけられる時間。 |
| ピック&プレース | 部品を取って移動・配置する動作。 |
| 協働ロボット(Cobot) | 作業者と並んで作業できる安全設計のロボット。 |
| MES(製造実行システム) | 現場の生産状況を可視化・管理するシステム。 |
5. 実際の現場で見るべきポイント
自動化の理解は「座学」だけではなく、現場で観察・体験することが最も重要です。以下のような視点を持ちましょう。
● どこに“ムダ”があるかを見る目
- 余分な動作、待ち時間、歩行、取り間違い
- ムダを見つけることで、自動化の「導入すべき場所」が見えてきます
● 人と機械の関係性を見る
- 人が苦労している部分を、機械が助けてくれているか
- 機械が原因でかえって作業者のストレスが増えていないか
● 安全対策を意識する
- 非常停止ボタンの位置
- センサーやライトカーテンによる接触防止機構
- 教育や指導が適切に行われているか
6. 自動化を学ぶための基本ステップ
● ステップ1:現場を知る
実際の作業工程を理解する。可能なら現場体験やOJTを受ける。
● ステップ2:基礎制御の学習
- シーケンス制御(リレー・タイマー・条件分岐)
- PLCのラダー図を読む練習を始めてみる
● ステップ3:簡単な改善提案を考える
- 例えば「部品供給を台車からボックスへ変えるだけで負荷が減る」など
- 小さな改善でも、現場にとっては大きな効果につながることが多い
● ステップ4:IT・IoTの基礎を学ぶ
- センサーデータの活用
- クラウド連携やダッシュボードの基礎知識
7. 若手技術者が活躍するための心構え
- 「分からないことを聞ける力」が一番大事
- 周囲のベテランから素直に学び、吸収する姿勢を持つ
- 最新の技術動向にもアンテナを張っておく(展示会、Web記事など)
- 「なぜこの機械がここにあるのか?」という視点を持つ
まとめ
工場の自動化は、単なる機械導入ではなく、現場の課題を“技術で解決する”プロセスです。若手技術者がその一端を担うためには、「設備の仕組み」「現場の動き」「改善の考え方」など、技術と現場の橋渡しができる力が必要です。
まずは基本を押さえ、現場をよく観察し、小さな改善を提案するところから始めてみましょう。
“自動化のプロ”への第一歩は、今日からでも踏み出せます。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。