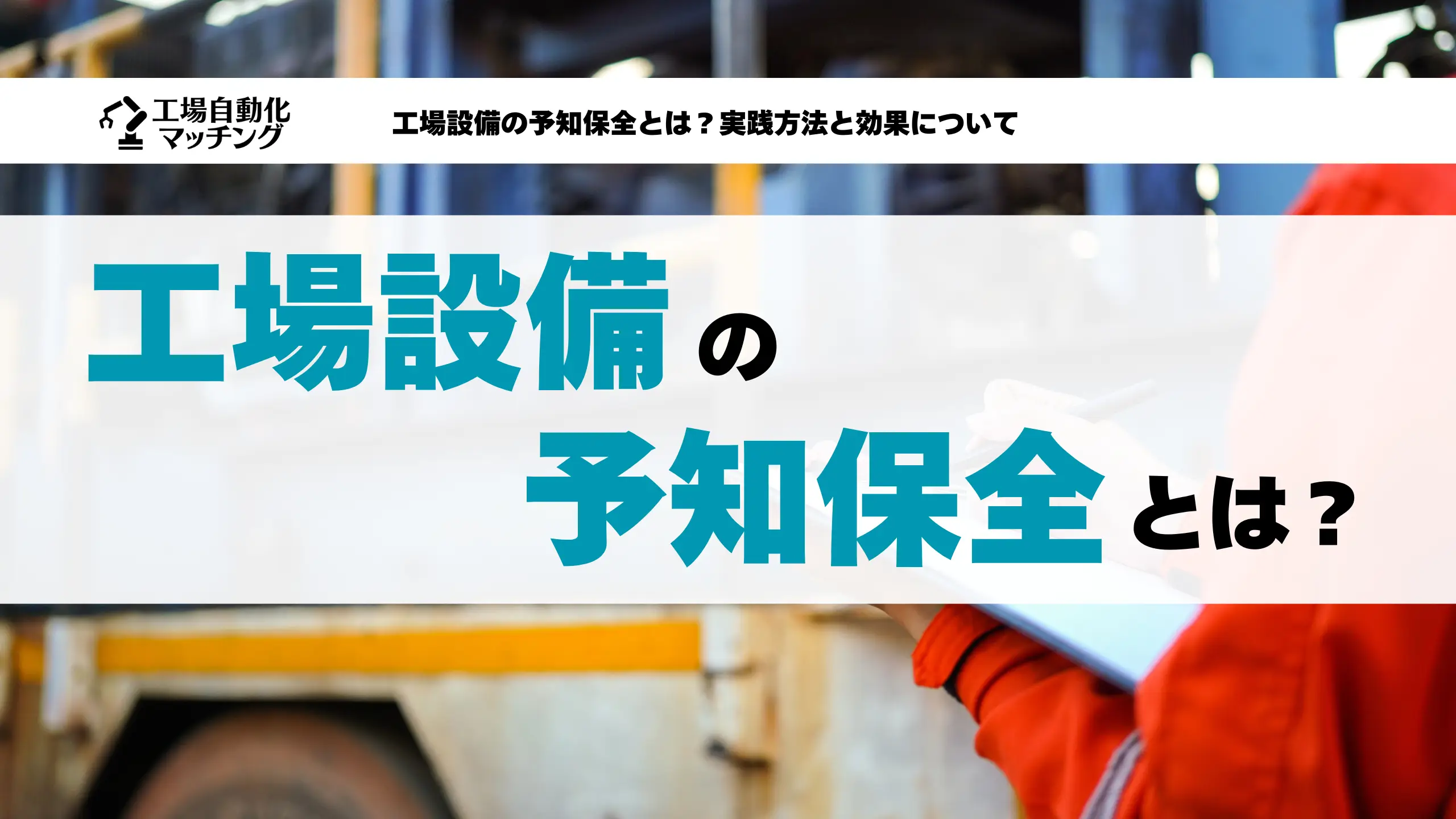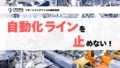工場の設備や機械は、日々の生産活動において重要な役割を果たしています。しかし、これらの機器は使用を続けることで徐々に劣化し、時には突然の故障を引き起こすこともあります。特に、自動化が進む工場では、ひとつの設備の停止が全体の生産ラインに大きな影響を与えることがあります。
こうしたリスクを回避するために注目されているのが「予知保全(Predictive Maintenance)」です。本記事では、初心者の方にも分かりやすく、予知保全の概要や実践方法、導入による効果について解説します。
予知保全とは?
予知保全とは、設備や機械が故障する前に、その兆候を見つけて事前にメンテナンスを行う手法です。これにより、突然の機械トラブルや生産ラインの停止を未然に防ぎ、設備の稼働率を高めることができます。
予知保全と他の保全手法の違い
| 保全手法 | 特徴 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| 事後保全 | 故障が発生してから修理を行う | 故障発生後 |
| 予防保全 | 一定の期間ごとに定期的なメンテナンスを行う | スケジュールに基づく |
| 予知保全 | センサーやデータ分析により、故障の兆候を検知して対応 | 故障予兆を検知した時点 |
予知保全は、データに基づいた「予測」を行う点で、従来の事後保全や予防保全とは異なります。特にIoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の技術を活用することで、精度の高い予測が可能です。
予知保全の実践方法
1. センサーの設置とデータ収集
まず、設備や機械にセンサーを設置します。センサーは、以下のようなデータを収集します。
- 温度: モーターや部品の過熱を検知
- 振動: 機械内部の異常や摩耗を察知
- 音: 異常な動作音や摩擦音を検出
- 電流・電圧: モーターや制御装置の異常を確認
2. IoTプラットフォームでデータ管理
収集したデータは、IoTプラットフォームに集約されます。プラットフォーム上でデータを可視化することで、設備の状態をリアルタイムで監視可能です。
- ダッシュボード: 温度や振動などのデータをグラフ化し、変化を一目で確認
- アラート機能: 異常な数値が検出された場合、担当者に通知
3. AIを活用したデータ分析
AIや機械学習(Machine Learning)を活用することで、過去のデータと比較し、異常なパターンを検出します。また、故障の予測も可能になります。
- 異常検知: 通常とは異なる振動パターンを検出
- 予測メンテナンス: このまま稼働を続けると何日後に故障するかを予測
4. 予知保全の実施
AIが故障の兆候を検知した場合、メンテナンスを実施します。具体的には以下のような対応が考えられます。
- 部品交換: 摩耗したベルトやギアを交換
- 潤滑油の補充: 可動部に潤滑油を塗布して摩擦を減少
- 動作調整: センサーや機械の設定を最適化
予知保全の導入事例
事例1: 自動車部品製造工場での予知保全システム導入
背景: 生産ラインのモーターが頻繁に故障し、修理コストが増加していた。
導入内容: モーターに温度と振動センサーを設置し、IoTプラットフォームとAI解析を導入。
結果:
- モーターの故障頻度が50%減少
- 突発的な停止がなくなり、生産性が20%向上
- メンテナンスコストの削減にも成功
事例2: 食品工場の自動包装機での活用
背景: 包装機のベルトが突然切れ、生産ラインが停止するトラブルが多発していた。
導入内容: ベルトの張力や摩耗状態を監視するセンサーを設置。異常を検知すると自動的にメンテナンス指示が出る仕組みを構築。
結果:
- 突然のベルト破損がなくなり、計画的な部品交換が可能に
- 包装機の稼働率が向上し、出荷遅延のリスクが減少
- 予備部品の在庫管理も最適化
予知保全を導入する際のポイント
1. まずは重要機器から導入する
すべての設備に予知保全を導入するのはコストがかかります。まずは、生産ラインのボトルネックになりやすい機器や、故障すると影響が大きい設備から導入するのが良いでしょう。
2. メンテナンス計画と組み合わせる
予知保全を導入しても、実際のメンテナンスを実施しなければ意味がありません。予測されたタイミングで確実にメンテナンスを行う計画を立て、定期的な点検も組み合わせることが重要です。
3. スタッフの教育とサポート体制を整える
AIやIoTを活用することで、より高度な機器管理が可能になりますが、現場スタッフが使いこなせなければ効果は半減します。新しいシステムの操作方法や、アラートが出た際の対応手順を事前に共有しておきましょう。
まとめ
予知保全は、工場設備の故障を未然に防ぎ、安定した生産活動を支えるための強力な手法です。特に、IoTセンサーやAI技術を活用することで、従来の予防保全以上に精度の高いメンテナンスが可能になります。
導入事例でも紹介したように、予知保全を実施することで、機器の稼働率向上やコスト削減、さらには安全性の向上にもつながります。また、初めて導入する場合は、重要な機器から始め、徐々に適用範囲を広げることで、効果を実感しやすくなります。
これから予知保全を検討している企業の皆様も、ぜひ今回の記事を参考に、安定した生産体制と効率的な設備運用を実現してください!

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。