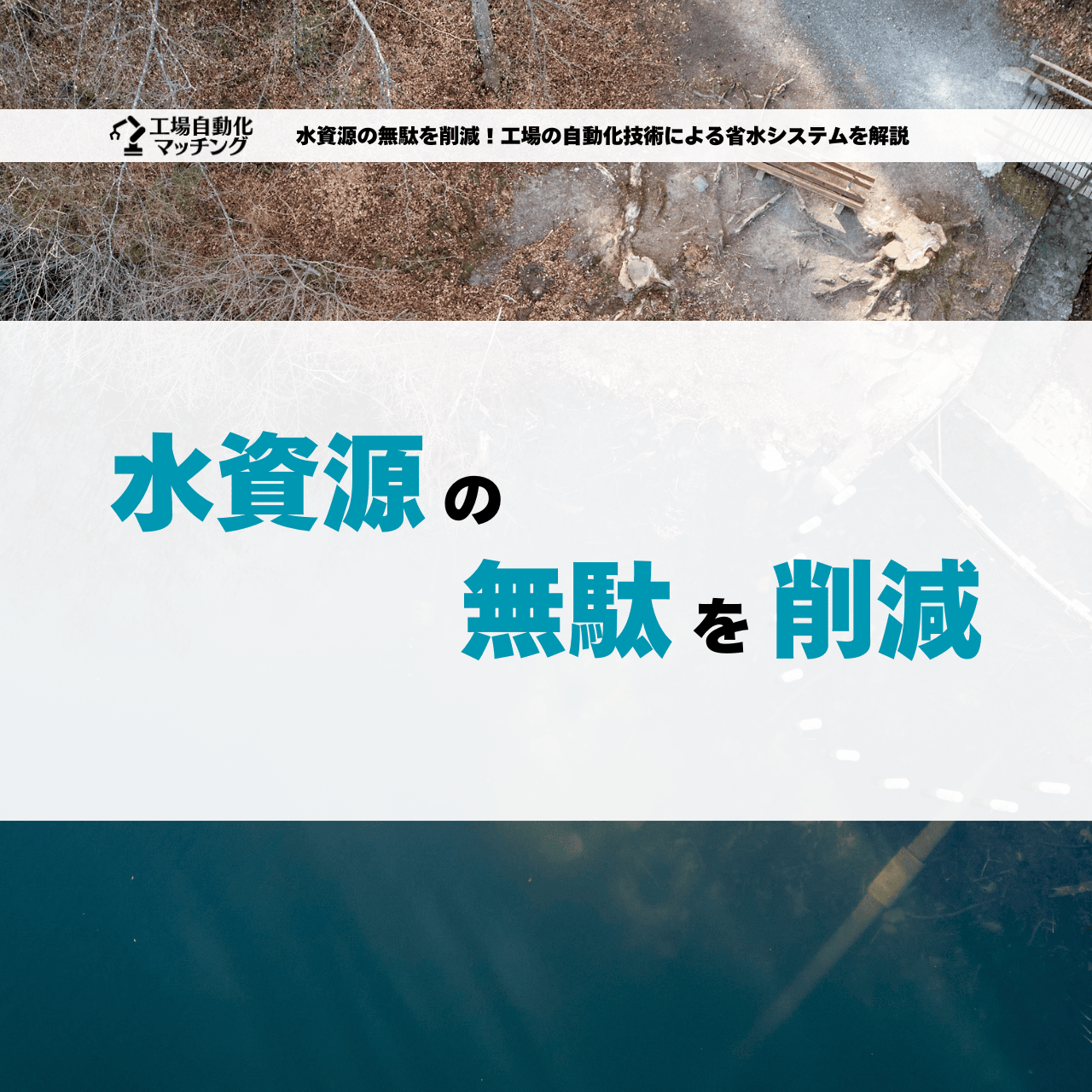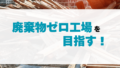はじめに
水はすべての産業活動に欠かせない資源です。とくに食品、化学、製紙、繊維などの製造業では、洗浄・冷却・加熱・原材料など多くの用途で水を大量に使用します。
しかし、世界的な水不足や環境問題への関心が高まる中、水資源の有効活用が求められています。そんな中で注目されているのが、自動化技術を活用した省水システムです。
本記事では、初心者の方にもわかりやすく、自動化によって水の無駄を削減する仕組みや技術、導入メリット、具体的な事例などを解説します。
なぜ工場で「省水」が重要なのか?
製造業において水資源が重要視されている理由は、以下の通りです。
- 水道代や地下水くみ上げコストの上昇
- 排水処理にかかるエネルギーや薬品コスト
- 地域の水不足による生産制限リスク
- 環境配慮企業としての社会的信頼の向上
つまり、水を無駄なく使い、必要な量だけを使うことが、コスト削減と企業価値の向上につながるのです。
工場における水の主な用途
- 製品や原料の洗浄
- 加熱や冷却のための熱交換
- 製品の成分(水を含む飲料や食品)
- ボイラーや冷却塔などの設備運転
- 排水処理・リサイクル用の処理水
このように水はさまざまな工程で使われており、その使用量を減らすことは多方面にメリットをもたらします。
自動化による省水システムの主な仕組み
1. 水使用の「見える化」
流量センサーや水質センサーを使って、どこでどれだけの水が使われているのかをリアルタイムで把握できるようにします。
- 部門・装置別の水使用量を記録
- 漏れや過剰使用を即時検知
- 改善箇所を特定しやすくなる
2. 自動制御バルブによる最適供給
設備や製品に必要な水量をあらかじめ設定しておき、必要なときに必要な量だけ水を供給する制御バルブを自動化します。
- 洗浄時間や使用水量の自動最適化
- 空運転・流しっぱなしを防止
- 使用条件に応じた柔軟な制御が可能
3. 再利用システムの自動管理
一度使った水をろ過・沈殿・殺菌などで処理し、再利用可能な状態にして再度使用する自動リサイクルシステムです。
- 排水の自動分析と再利用可否の判断
- 洗浄水や冷却水のリユース率を向上
- 新水の使用量を削減
導入事例で見る省水の効果
事例①:飲料メーカーA社の洗浄工程自動化
課題:製品切り替え時のライン洗浄で大量の水を使用
対策:流量センサーとタイマー制御を導入し、洗浄水の使用量を自動最適化
効果:年間約35%の水使用量削減。洗浄時間も20%短縮。
事例②:化学工場B社の冷却水リサイクル
課題:冷却塔からの排水量が多く、水道代と処理費が高騰
対策:排水の水質を自動監視し、基準を満たせば再利用
効果:新水使用量を50%以上削減。排水処理費用も大幅減少。
導入のステップとポイント
1. 現状の水使用量を把握する
まずは「どこで・どのくらい水を使っているか」を数値で把握することが重要です。省水の第一歩は、データの可視化(見える化)です。
2. ムダを見つける
- 水が出しっぱなしになっていないか
- 同じ工程で過剰な洗浄が行われていないか
- 排水にまだ使える水が混ざっていないか
こうした「なんとなく使っている水」を、センサーや自動制御で見直しましょう。
3. 小規模から導入し効果を測定
全体に一気に導入するのではなく、水使用量が多い工程から小規模に試験導入し、改善効果を検証しましょう。
4. 教育と意識づけも大切
自動化に加えて、現場の従業員にも「水を無駄にしない意識」を共有することで、より大きな成果が得られます。
今後の技術進化と展望
今後は以下のような技術がさらに発展し、より効率的な水資源管理が可能になると期待されています。
- AIによる水使用の最適予測と制御
- リアルタイム水質分析による自動判断
- IoT連携による複数工場での一元管理
- 雨水や排熱を活用した循環型の水利用
これらの技術によって、水資源の持続可能な活用がますます現実のものになっていくでしょう。
まとめ
水資源は有限であり、工場が使う水にも責任が求められる時代です。自動化技術を活用した省水システムは、水の無駄を減らし、環境への配慮とコスト削減を両立できる有効な手段です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 水の見える化 | 使用量・水質・流量をリアルタイムで監視 |
| 自動制御 | 必要なときに必要な水量だけを供給 |
| 再利用 | 一度使った水を自動的に処理・再利用 |
| 効果 | 水道代削減・排水処理費削減・環境負荷低減 |
まずは自社の水の使い方を見直し、小さな自動化から始めてみることで、持続可能な工場運営への第一歩を踏み出しましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。