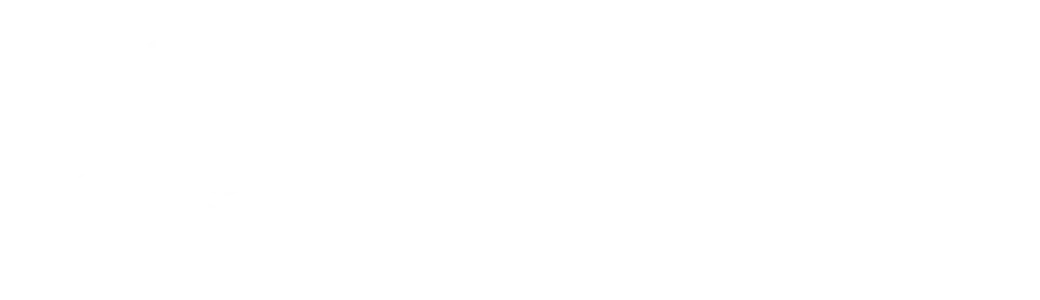日本の製造業が世界に誇る“カイゼン(改善)”活動。現場の知恵や創意工夫によってムダを減らし、品質・生産性を高める文化です。一方で、近年はロボットやIoT、AIなどを活用した“自動化”も注目を集めています。
この2つの取り組み、実は「対立」ではなく、「組み合わせることで大きな力を発揮する」ものです。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、カイゼン活動と自動化をうまく融合させる仕組みと考え方を紹介します。
カイゼンと自動化、それぞれの役割
■ カイゼンの特長
- 現場主導での継続的な改善
- 少ないコストで効果を出す
- 作業者の気づき・意欲を育てる
■ 自動化の特長
- 一定の初期投資で大幅な効率化
- 精度の高い作業の再現が可能
- 人手不足や属人化の解消
つまり、カイゼン=柔軟な改善、自動化=安定的な改善という位置づけです。
よくある失敗:「カイゼン vs 自動化」になってしまう理由
- 自動化を導入したことで、カイゼンの余地がなくなったと感じられる
- 機械が動いているため、「もう改善できない」と思われる
- 現場が「機械化は上層部の仕事」と捉え、他人ごとになってしまう
このような状態では、自動化の真の効果は発揮されません。
相乗効果を生む仕組みづくりのポイント
✔ ポイント①:自動化も“改善対象”とする文化
「機械があるからもう終わり」ではなく、「機械をどう活かすか」を考えるカイゼンに転換します。
- センサー位置の見直し
- ロボットの動作時間短縮
- ソフトのUI変更による操作性向上
など、“機械も改善できる”という意識を持つことが第一歩です。
✔ ポイント②:カイゼン活動の中に「自動化視点」を取り入れる
- 人が何度も同じ作業をしている → 自動化できないか?
- 作業にムダが多い → 自動化すれば安定するかも?
- 不良の原因が属人的 → センサーで測れないか?
このように、改善テーマに「自動化で解決できるか?」という視点を加えるだけで、可能性が広がります。
✔ ポイント③:カイゼンチームと自動化担当の連携強化
- カイゼン提案のうち、自動化が有効なものはIT・保全チームへ
- 自動化後の運用については、カイゼンチームがフォロー
- 成果は合同で発表し、「一緒にやった」達成感を共有
この連携によって、改善のスピードと幅が大きく広がります。
成功事例:電子部品工場(従業員120名)
■ 背景
作業者から「ネジ締めに時間がかかる」というカイゼン提案が多数。
■ 取り組み
- カイゼン会議で「協働ロボットによるネジ締め」を提案
- テスト導入後、改善チームとロボット担当が一体で改良(ツール交換・動作短縮)
■ 成果
- 工数25%削減
- 作業者の疲労軽減
- 改善件数も前年比130%に増加
自動化による改善を“見える化”する方法
- カイゼン報告書に「自動化による改善項目」欄を設ける
- Before/Afterの動画を社内共有
- 改善発表会で「自動化を絡めた取り組み」にポイント加点
これにより、現場の関心が「自動化は遠い話」から「自分たちの改善手段」へと変わります。
教育と仕組みがカギになる
- カイゼン担当に「自動化の基礎教育」を実施(AI、PLC、ロボットなど)
- 自動化担当にも「現場のカイゼン文化」の理解を促す
- 改善提案フォームに「自動化のアイデア」欄を追加
こうした教育と仕組みが、「カイゼン×自動化」の発想を促します。
まとめ
カイゼンと自動化は、別々の取り組みではなく、組み合わせることで最大限の効果を生むパートナーです。
“人の知恵”と“機械の力”を両立させることが、これからの製造業に求められる競争力の源泉になります。
まずは、自動化も「改善できる対象」であると認識し、カイゼン活動の一部として組み込んでいきましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。