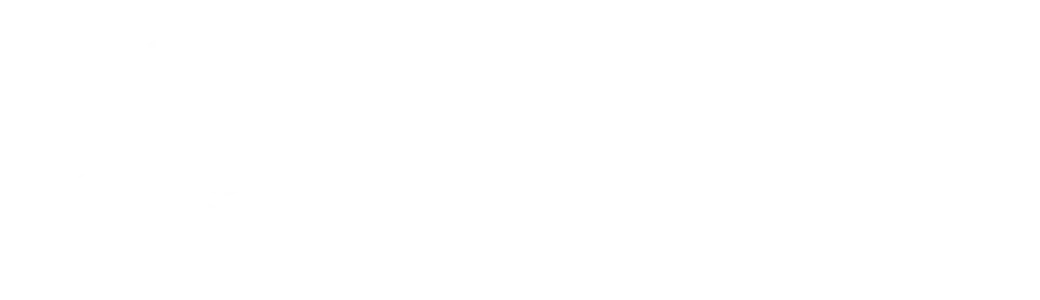多品種少量生産が当たり前になった今、製造現場では「段取り替え」が大きな負担となっています。
金型交換、治具変更、レシピ切り替えなど、1回の段取りに数分〜数時間を要する場合も少なくありません。
この“段取り時間”をゼロに近づける取り組みが、今注目されています。
キーワードは「段取り替えゼロ」=段取りレス自動化です。
この記事では、「段取り替えを極限まで減らす自動化設備の導入ポイント」を、初心者にもわかりやすく解説します。
段取り替えがもたらす3つのロス
まず、段取り替えによって現場でどんな“損失”が発生しているかを整理しましょう。
生産停止による時間ロス
段取り中は設備が稼働できません。生産計画がタイトなほど、この“ロスタイム”が大きな問題になります。
人的負担(熟練者依存)
段取り作業は多くの場合、熟練作業者に依存しており、技術継承・属人化のリスクを抱えています。
品質リスク
段取り後の初品確認や設定ミスなど、品質トラブルの温床にもなります。
これらのロスを削減するには、段取り替えそのものをなくす=ゼロ段取り化の発想が必要です。
段取りレスを実現する自動化のアプローチ
段取りを減らすために有効な自動化技術を紹介します。
多品種対応の「自動ツールチェンジ」
- ロボットアームが工具や治具を自動交換
- タレット式工具台や自動クランプ装置を使い、1台で複数製品に対応可能
セル生産+協働ロボットの組み合わせ
- 柔軟なレイアウトで、製品ごとのライン変更なしで対応
- 人が対応する必要があった部分も、協働ロボットと分担することで段取り時間を削減
自動認識システム(画像処理・RFID)
- 製品や材料をセンサーやカメラで自動認識し、レシピや加工条件を自動で切り替え
- 手動の型番確認・条件入力が不要に
スケジューラー連携型の「レシピ自動切替」
- 生産指示と設備のプログラムを連携し、作業者が操作しなくても条件が切り替わる仕組み
- MES・ERPと設備がつながる“スマートファクトリー化”の第一歩
導入の際に押さえておきたい設計ポイント
段取りレスを実現するには、単に自動機を導入するだけでなく、設計段階での工夫が不可欠です。
✔ 製品ごとの差異を「段取りなしで吸収できる」ように
- 寸法の違い:可動ストッパー、サーボ駆動
- 工程の違い:分岐ラインやバイパス設計
- 加工条件の違い:インターフェースで自動選択
✔ 「1人でも対応できる」設計に
- 操作画面に全ての切り替えボタンを集約
- 初心者でも理解できるカラーガイドや動画説明付きHMI
✔ 「段取り替えが要らない」スケジュール設計
- 製品順にラインを並べる(段取り順を考慮した順番)
- 製品サイズや工程の近いものをまとめて生産するなど、段取りを極力省く工夫も重要です
段取りレス化の導入事例:板金加工会社B社
B社では、これまで1日3回行っていた金型交換の段取りに、平均30分かかっていました。
しかし以下の設備導入によって、段取り時間はほぼゼロに。
- 金型自動交換装置
- 自動搬送+画像認識による部品判別
- タッチパネルによるレシピ自動呼び出し
結果:
- 1日の稼働時間が+90分向上
- ベテラン不在時の品質・段取りミスがゼロに
- 年間での設備稼働率が10%以上アップ
段取りレス化を始めるための第一歩
いきなり「完全段取りレス」は難しい場合、以下のような小さな一歩から始めるのも有効です。
- 治具のクイックチェンジ化
- 作業手順書を動画化・標準化
- ロット切り替え時の設定記録を自動化
段取り替えに関する作業を「誰が何分で何をしているか」を分析することで、改善ポイントの優先順位が見えてきます。
まとめ:「止まらない工場」を目指して
段取りレス化は、単なる時短ではありません。
生産の柔軟性、技術の標準化、品質の安定、そして競争力の源泉です。
- 多品種対応
- 少人化・省力化
- ミスの予防
- 生産計画の柔軟性向上
これらを同時に達成するために、「段取り替えゼロ」の思想を取り入れた自動化は、これからの工場づくりの大きな武器となります。
まずは、目の前の段取り作業を「なくせないか?」という視点で見直してみましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。