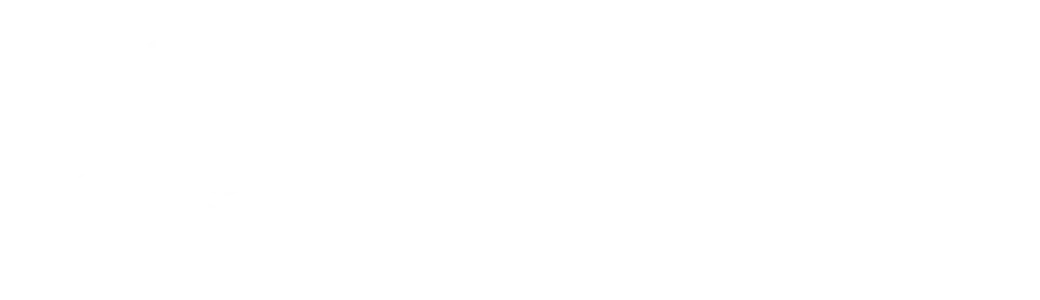日本は地震大国です。工場の自動化が進んでも、自然災害は避けて通れません。特に地震発生時、稼働中の機械や搬送ラインがそのまま動き続けると、製品の破損や機器の損傷、さらには作業者の巻き込まれ事故につながる危険があります。
そこで求められるのが、「地震時の自動停止設計」と「復旧までの安全なプロトコル」です。
本記事では、初心者の方にもわかりやすくその考え方と設計方法を解説します。
地震時に想定される被害
地震が発生した際、工場内で起きるリスクは以下のようなものがあります。
- 機械の転倒・位置ズレ
- ワーク(製品)の落下や破損
- 電源遮断や通信断による誤動作
- 作業者の安全確保の遅れ
これらを防ぐためには、ラインを「自動で確実に停止させる仕組み」と「人が安全を確認した上で復旧できる仕組み」が必要です。
自動停止の基本設計
加速度センサの活用
地震の揺れをリアルタイムに検知するために、各設備または建屋全体に「加速度センサ(地震センサ)」を設置します。
一般的には震度5弱以上を閾値とし、それを超えると「地震発生」信号を出力します。
安全停止信号の統合
加速度センサの出力をPLCや安全リレーに接続し、全設備に一斉停止信号を送信します。
これにより、ラインが強制的に停止し、動力が遮断されます。
非常停止とは別系統に
地震による停止は、非常停止(エマージェンシーストップ)とは別の“自動停止信号”として設けるのが理想です。
これにより、混同や誤復旧を避けられます。
地震停止後の復旧プロトコル
ラインが安全に停止した後、次に重要になるのが「いつ、どのように再稼働させるか」という復旧手順です。
人的確認のフローを挟む
センサが「揺れが収まった」と判定しても、即自動で再稼働させるのは非常に危険です。必ず以下のようなフローを設けます。
- 作業責任者が現場の被害確認を行う
- 制御盤またはHMIから「復旧操作」を明示的に行う
- リセット後、初期状態からソフトスタート
設備のズレ・損傷チェック
搬送装置やロボットアームなど、位置ズレが発生していないかを目視・センサで確認します。
復旧前に「基準位置への復帰動作」を自動実行させることも有効です。
ログと履歴の保存
地震による停止と復旧は、必ずログとして残し、後日の保全点検やBCP(事業継続計画)にも活用しましょう。
デジタルでの履歴管理が望ましいです。
安全のための補足設計
- UPS(無停電電源装置): 停電時にも安全停止動作が完了するように
- ブザー・警告灯: 地震停止中の警告を現場に周知
- マニュアル表示: 復旧手順をHMI画面や印刷物で即確認できるように
これらを事前に整えておくことで、慌てることなく冷静に対応が可能になります。
まとめ:止める設計、再開する設計
地震はいつ、どこで起きてもおかしくありません。だからこそ、工場の自動化ラインは「いざというときに止まる仕組み」と「安全を確認した上で再開できる設計」をあらかじめ持っているべきです。
止める・見極める・戻す。そのすべてを含めた“地震対応の設計”が、真に信頼される自動化ラインには必要なのです。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。