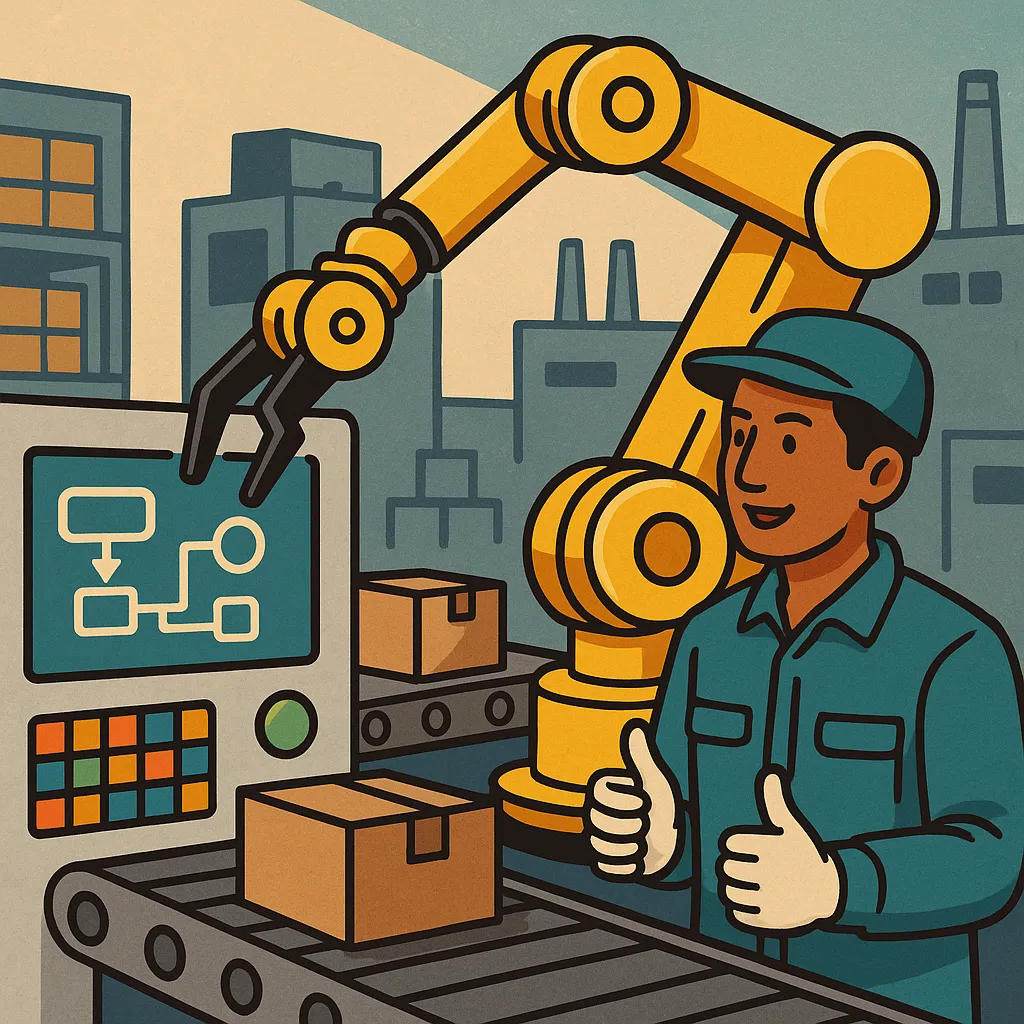製造業において外国人労働者の受け入れが年々増加しています。
背景には、国内労働力の減少、技能実習制度の拡充、企業のグローバル化などがあります。
一方で、現場では「日本語が通じにくい」「指示が伝わらない」「ミスが起こる」といった言語に関する課題が顕在化しています。
そこで注目されているのが、自動化との融合による“言語に依存しない現場設計”です。
この記事では、自動化と外国人材の活用を両立させるための方法を、初心者向けにわかりやすく解説します。
外国人材活用の現場で起きやすい問題とは?
まずは、言語に起因するトラブルを整理してみましょう。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 作業指示が正確に伝わらない | 「ここまでやって」「注意して」など抽象表現が通じにくい |
| マニュアルの読解が困難 | 漢字や敬語表現が多く、理解に時間がかかる |
| トラブル時の報告が遅れる | 言葉に詰まり、異常を見逃すリスク |
| 作業の定着に時間がかかる | 毎回の指導が属人的になり、教育負荷が高い |
これらの問題は、「作業者が外国人であること」そのものが原因ではなく、現場の設計が“言語に依存しすぎている”ことが根本です。
自動化が言語障壁を乗り越える鍵になる理由
自動化の導入により、次のようなメリットが生まれます。
■ 1. 操作手順の“視覚化”と“統一”
- タッチパネルに「絵+色分け+番号」で手順を表示
- 動画で作業フローを流すことで、文字を読まなくても理解可能に
→ 視覚で伝えることで、言語力に依存せずに作業が覚えられる
■ 2. 作業をAIがガイドする「音声ナビ+センサー制御」
- 作業者が工程を進めると、センサーが次の作業を検知し、音声で案内
- 「赤い箱を開けてください」など、簡単な言葉で補助
→ 迷わずに次の行動が取れ、ミスが減る
■ 3. 自動化による“判断作業”の代替
- 検査、検品、数量確認など、個人の判断が必要な工程をロボット化
- 作業者は“物を置く・取る”だけに集中できる
→ 作業負担を減らし、技能の差をなくすことが可能に
現場での具体的な工夫と事例
■ 多言語対応+アイコン表示のタッチパネル
- 日本語/英語/ベトナム語/ネパール語などに切替可能
- 各工程を「写真+番号+図」で表現
→ 操作説明が不要になり、教育期間を半分以下に短縮
■ LEDによる作業支援(ピッキングや検査)
- 必要な部品に光を当てて示す(ライトガイド方式)
- 説明は不要、視覚で即座に理解
→ 初日から作業に参加でき、戦力化が早い
■ 作業者による入力をなくす自動記録
- 生産実績や検査結果は設備側が自動で記録
- 作業者は「開始」「完了」だけ押すだけ
→ ミスが減るうえ、報告書作成も不要に
注意すべきポイント
■ ① 翻訳に頼りすぎない
多言語対応は有効ですが、翻訳精度や文脈の違いで誤解が生まれることもあります。
→ 言葉に頼らない“構造で伝える”設計が理想
■ ② 技能の習得機会を奪わない工夫も重要
すべてを自動化してしまうと、人が考える余地がなくなり、成長が止まることも。
→ 難易度別に自動化のレベルを調整し、ステップアップできる仕組みを残す
■ ③ コミュニケーションの“場”は別に設ける
現場が“無言”になりすぎないよう、朝礼や共有の場では通訳ツールなどを活用して会話機会を設けることも大切です。
自動化で広がる多様な働き方
外国人材に限らず、高齢者・障がい者・子育て世代など多様な人が働く現場においても、言語に依存しない設計は大きな可能性を秘めています。
- スキルに応じて作業内容をカスタマイズ
- 工程をAIが見守ることで、安心して働ける環境
- 失敗してもフォローが自動化されている仕組み
→ 自動化は“人を減らす”のではなく、“人を活かす”手段となり得ます。
まとめ
言語に頼らない現場づくりは、単に「外国人のため」ではありません。
それは、誰もが分かりやすく、安全に、安定して働ける環境を実現するための第一歩です。
自動化と外国人材の活用は対立する概念ではなく、むしろ両立させることで現場の柔軟性と持続性が高まるのです。
今後、ますます多様化が進む製造現場において、“誰でも使える設計”という視点は避けて通れません。
まずは1つの工程から、「言葉がなくても通じる現場」づくりを始めてみてはいかがでしょうか?

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。