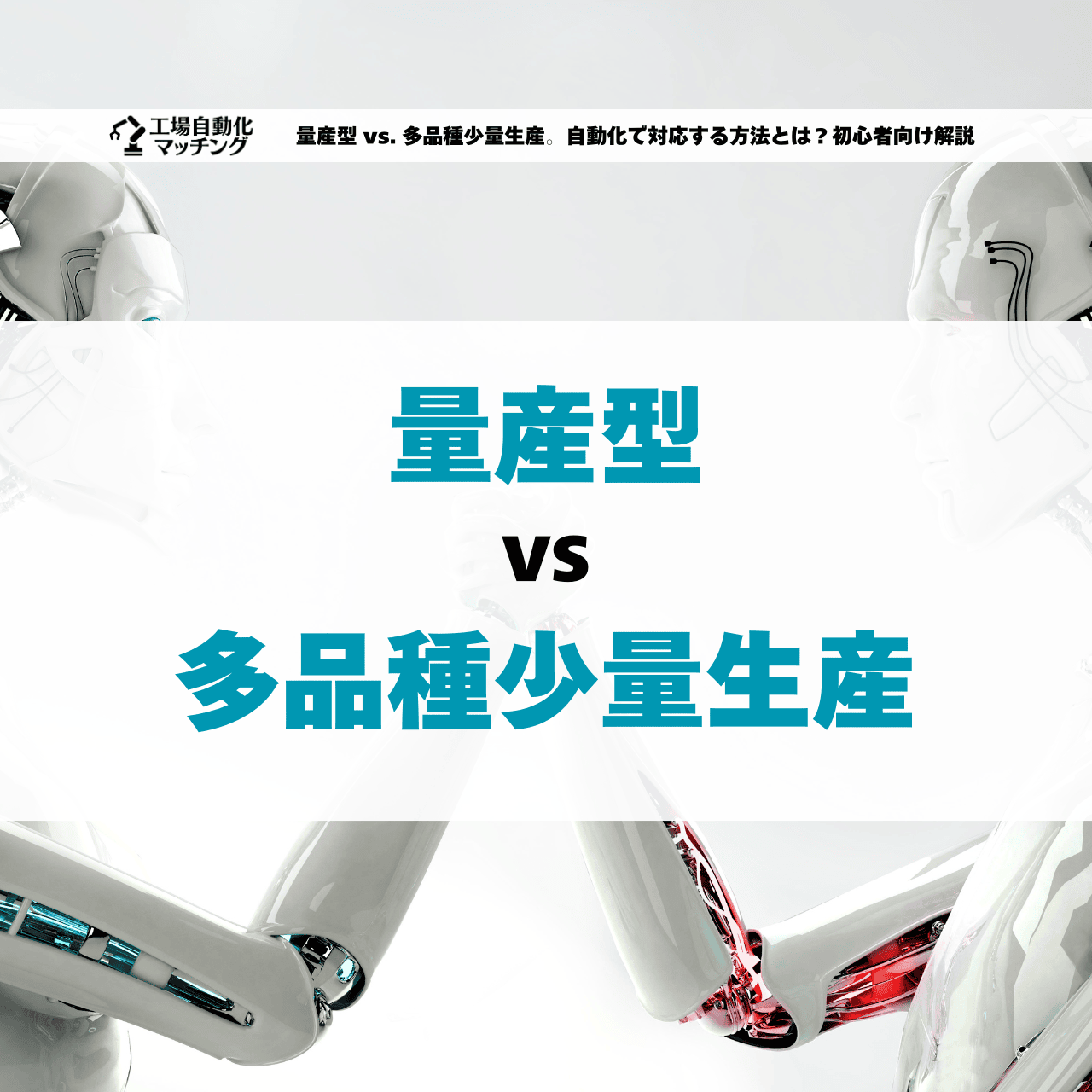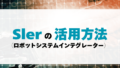はじめに
工場の自動化を考えるうえで、まず整理しておきたいのが「量産型」と「多品種少量生産」という2つの生産スタイルです。
製造業では、製品の種類と生産量に応じて、自動化の手法や導入する機器の選び方が大きく異なります。
「うちは小ロットの注文が多いから自動化は難しいのでは?」
「量産品しか自動化できないと思っていた」
そんなお悩みを持つ方のために、本記事では量産型と多品種少量生産、それぞれの特徴と自動化の対応方法を分かりやすく解説します。
1. 量産型と多品種少量生産の違いとは?
① 量産型とは?
量産型は、同じ製品を大量に・長期間にわたって生産するスタイルです。
✅ 特徴
- 製造工程が固定化されている
- 生産ラインの効率が高い
- 製品のバリエーションは少ない
✅ 代表的な例
- 自動車部品(ボルト、ナット、バンパーなど)
- 飲料や食品のパッケージ製品
- 樹脂製品や電子部品
② 多品種少量生産とは?
多品種少量生産は、多くの異なる製品を、少量ずつ生産するスタイルです。
✅ 特徴
- 設備や作業手順の切り替えが頻繁
- 納期や仕様が個別対応になることが多い
- 柔軟性の高い生産体制が求められる
✅ 代表的な例
- 試作品の製造
- カスタム家具・雑貨
- 特注機械・精密部品など
2. 自動化導入の考え方の違い
量産型に適した自動化の特徴
- 一度設定すれば、長時間稼働できる自動ライン
- 専用機を導入し、無駄を徹底排除
- スピードと効率を重視
💡 導入例
- コンベア式自動組立ライン
- ロボットによる溶接や塗装
- オートラベラーや包装機
多品種少量生産に適した自動化の特徴
- 柔軟性が高く、短時間で段取り変更できるシステム
- 作業指示や仕様変更に対応するAIやIoT
- 汎用性の高いロボットやプログラム切り替えがしやすい機器
💡 導入例
- 協働ロボット(コボット)による組立補助
- タブレット連携の作業支援システム
- AGV(無人搬送車)による個別ピッキング搬送
3. 自動化でそれぞれの生産方式に対応する方法
① 量産型の場合の自動化手法
| 自動化対象 | 技術や設備例 | メリット |
|---|---|---|
| 組立 | ロボットアーム、コンベアシステム | 大量生産に対応、一定品質 |
| 検査 | 画像検査装置、センサー | 不良品を早期発見 |
| 梱包 | 自動包装機、ラベリング機 | 労力削減、スピードアップ |
✅ ポイント
- ライン全体を一括で自動化しやすい
- 設備投資が大きいが、長期運用で回収可能
② 多品種少量生産の場合の自動化手法
| 自動化対象 | 技術や設備例 | メリット |
|---|---|---|
| 作業補助 | 協働ロボット(コボット) | 人との協働が可能、安全で柔軟 |
| 指示管理 | タブレット・IoTシステム | 製品ごとの仕様変更に対応 |
| 搬送 | AGV/AMR | 少量・個別品目にも対応可 |
✅ ポイント
- 人の作業を補助する自動化が中心
- 段取り替えや仕様変更への対応力が鍵
4. ハイブリッド型自動化という考え方
最近では、量産型と多品種少量型の中間に位置するハイブリッドな生産方式も増えています。
製品ごとに生産量が異なる中小企業では、一部の工程だけ自動化する部分導入が効果的です。
✅ 導入例
- 検査工程だけを自動化し、組立は人が行う
- 搬送だけAGVで自動化し、作業は柔軟に対応
- ロボット導入はしても、操作や段取りは人が担う
このような「人とロボットが協力する」スタイルが、特に中小企業において注目されています。
5. 導入時に考えるべきポイント
① 自社の生産スタイルを分析する
- 「量産向きか?多品種少量か?」をまずは把握
- 製品ごとの生産頻度やロット数を一覧にして整理
② 自動化の目的を明確にする
- 人手不足解消?
- 品質安定化?
- 作業の標準化?
- コスト削減?
目的が曖昧だと、必要以上の自動化設備を導入してしまうリスクがあります。
③ スモールスタートが基本
- まずは1工程だけ、1台だけの導入でもOK
- 効果が見えたら、徐々に拡張していくのが理想
まとめ
| 比較項目 | 量産型 | 多品種少量生産 |
|---|---|---|
| 生産量 | 多い | 少ない |
| 製品の種類 | 少ない | 多い |
| 自動化のしやすさ | 高い(専用設備向き) | 柔軟性重視 |
| 向いている自動化 | 完全自動化・専用ライン | 協働ロボット・IoT補助系 |
どちらの生産方式にも適した自動化手法は存在します。
自社の製品特性・現場の課題に合わせて、自動化を“部分導入”から始めることが成功のカギです。
今後の人手不足や品質向上のためにも、ぜひ自社に合ったスタイルで無理のない自動化を進めていきましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。