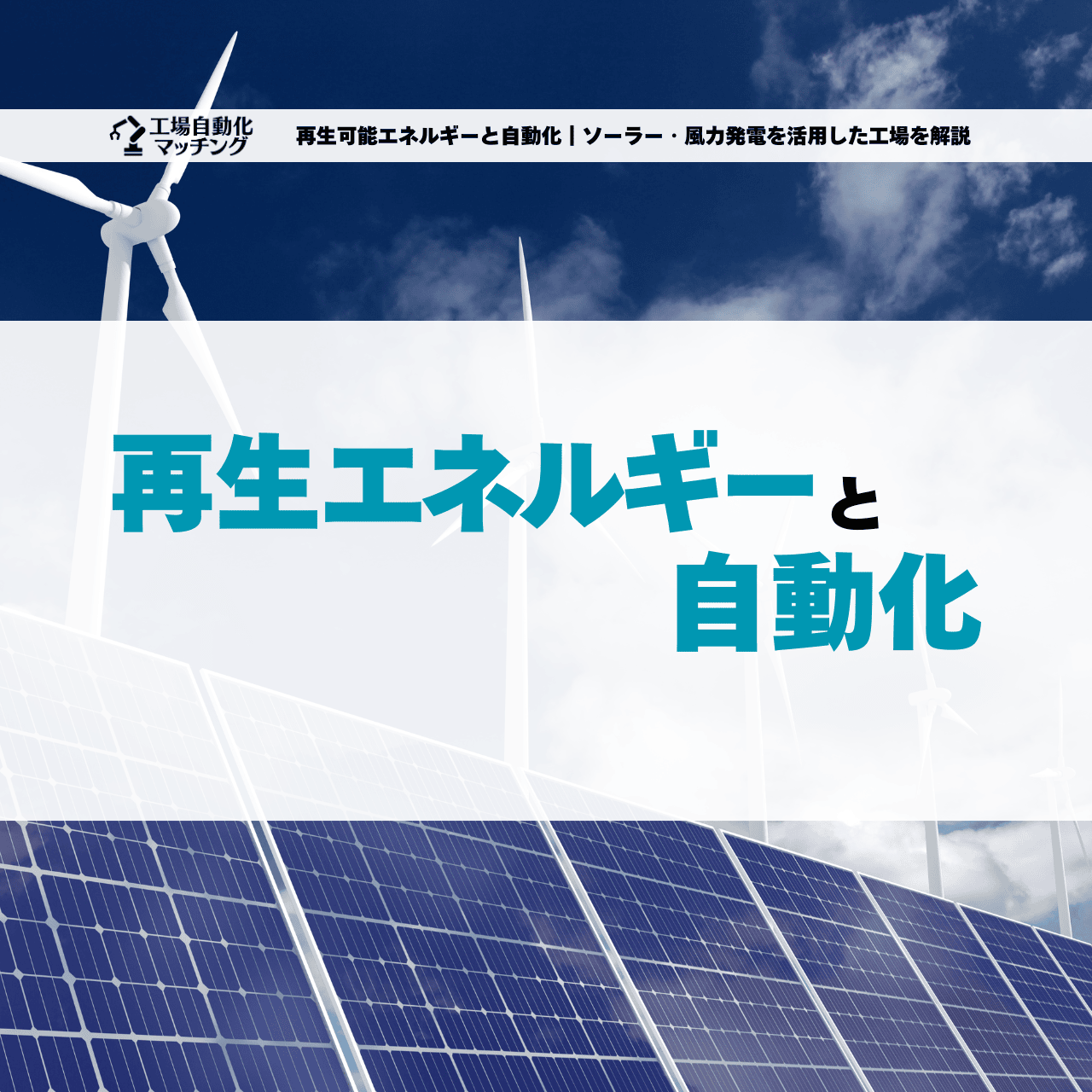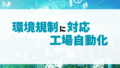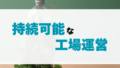環境問題やエネルギー価格の高騰が深刻化する中、製造業でも再生可能エネルギーの導入が急速に進んでいます。とくに太陽光(ソーラー)発電や風力発電は、持続可能なエネルギー源として注目されており、近年ではこれらの電力を活用した自動化工場が増えてきました。
この記事では、初心者の方にも分かりやすく、「再生可能エネルギー」と「自動化」が融合した次世代型工場の仕組みやメリット、導入のポイントを解説します。
再生可能エネルギーとは?
◆ 再生可能エネルギーの概要
再生可能エネルギーとは、地球上に常に存在し、枯渇せずに繰り返し使える自然由来のエネルギーのことです。
代表的なものは以下の通りです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 太陽光発電 | 屋根や空き地にパネルを設置して電力を生産 |
| 風力発電 | 風の力でタービンを回して発電 |
| 水力発電 | 水の流れを利用して電力を得る |
| バイオマス発電 | 廃材や食品残渣などを燃料に変える |
今回はこの中でも、とくに導入が進んでいる太陽光発電と風力発電を中心に取り上げます。
なぜ工場に再生可能エネルギーを導入するのか?
1. エネルギーコストの削減
発電設備の初期費用はかかりますが、長期的に見ると自家発電により電力コストを抑えることが可能になります。
2. 環境規制への対応
CO₂排出量の削減を求められる中、再生可能エネルギーは排出ゼロの電力源として有効です。
3. BCP(事業継続計画)強化
停電や災害時にも、独立した電源として活用できるため、生産の継続性が高まります。
自動化と再生可能エネルギーの関係
再生可能エネルギーと工場の自動化技術を組み合わせることで、以下のような相乗効果が得られます。
◆ エネルギー使用の最適化(EMS)
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)により、使用電力をリアルタイムで監視・制御
- 太陽光や風力発電の発電量に合わせて、設備の稼働を自動調整
◆ ピークシフト制御
- 発電量が多い昼間に自動でエネルギー消費の大きな工程を集中
- 夜間は発電した電力を蓄電池から供給する仕組み
◆ 設備の自動停止・再起動
- 電力供給が不足した場合、自動で一部機器の運転を停止
- 発電が安定したら自動で復旧
これにより、再生可能エネルギーの変動性をうまく吸収しながら、安定した工場運営が可能になります。
実際の導入事例
事例①:太陽光+蓄電池を導入した中小製造業(A社)
背景:電力料金の高騰とCO₂削減の社内目標達成が課題
対策:屋根に太陽光パネルを設置し、余剰電力を蓄電池に保存
自動化内容:発電量に応じて照明・空調・コンプレッサーなどの使用を制御
効果:電気代30%削減、CO₂排出量20%減少、停電時も生産継続可能に
事例②:風力発電で稼働する農業加工工場(B社)
背景:遠隔地にあり、電力インフラの整備が難しい地域
対策:小型風力タービンを設置し、オフグリッドでの稼働を実現
自動化内容:エネルギー使用を監視し、冷蔵設備の稼働時間を自動調整
効果:外部電力ゼロでの操業を達成し、CO₂排出をほぼゼロに
導入時のポイント
1. エネルギー使用量の見える化から始める
まずは自社の電力使用状況を把握することが重要です。どこで、いつ、どれだけ使っているかをデータ化しましょう。
2. 太陽光・風力の適正評価
設置場所の日照時間や風況データを調べ、どちらの発電方式が効果的かを判断する必要があります。
3. 蓄電池の導入検討
自然エネルギーは天候によって変動するため、蓄電池と組み合わせることで安定した運用が可能になります。
4. 自動制御システムとの統合
発電量・使用量・生産計画などの情報を連動させることで、省エネと安定稼働を両立できます。
今後の展望
再生可能エネルギーと自動化は、今後さらに進化していきます。
- AIによるエネルギー需要予測と最適制御
- 複数拠点の発電・消費情報をクラウドで一元管理
- 電力の地産地消モデルによる地域連携型工場
- 炭素クレジット取引への対応を視野に入れたデータ活用
これにより、単なる「エコ」ではなく、経済性と環境配慮を両立した次世代のスマート工場が広がっていくでしょう。
まとめ
再生可能エネルギーと自動化の融合は、これからの工場運営にとって欠かせない戦略です。持続可能な社会を支えながら、企業としてのコスト削減や生産効率化にもつながる実践的な取り組みと言えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 電力コスト削減、CO₂削減、災害時のBCP強化 |
| 自動化との連携 | 発電量に応じた設備制御、ピークシフト、省エネ運用 |
| 導入ステップ | エネルギーの見える化 → 発電方式の選定 → 自動化制御の導入 |
| 将来性 | AI活用・スマートグリッド連携・地域循環型モデルへの発展 |
まずは工場の屋根の太陽光パネル設置から、あるいはエネルギー監視システムの導入から始めてみてはいかがでしょうか? 小さな一歩が、将来の大きな持続可能性へとつながっていきます。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。