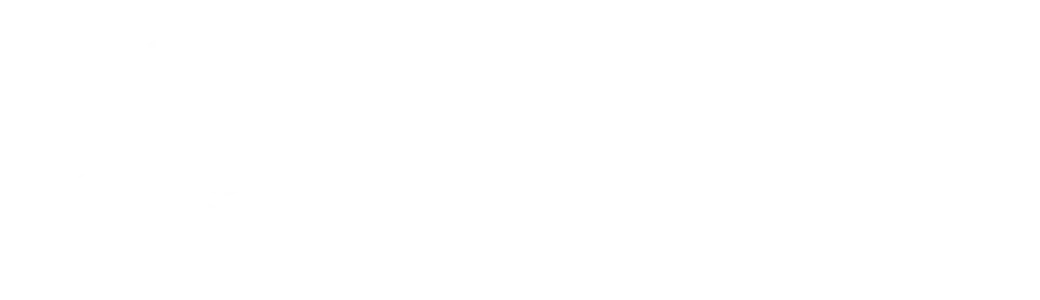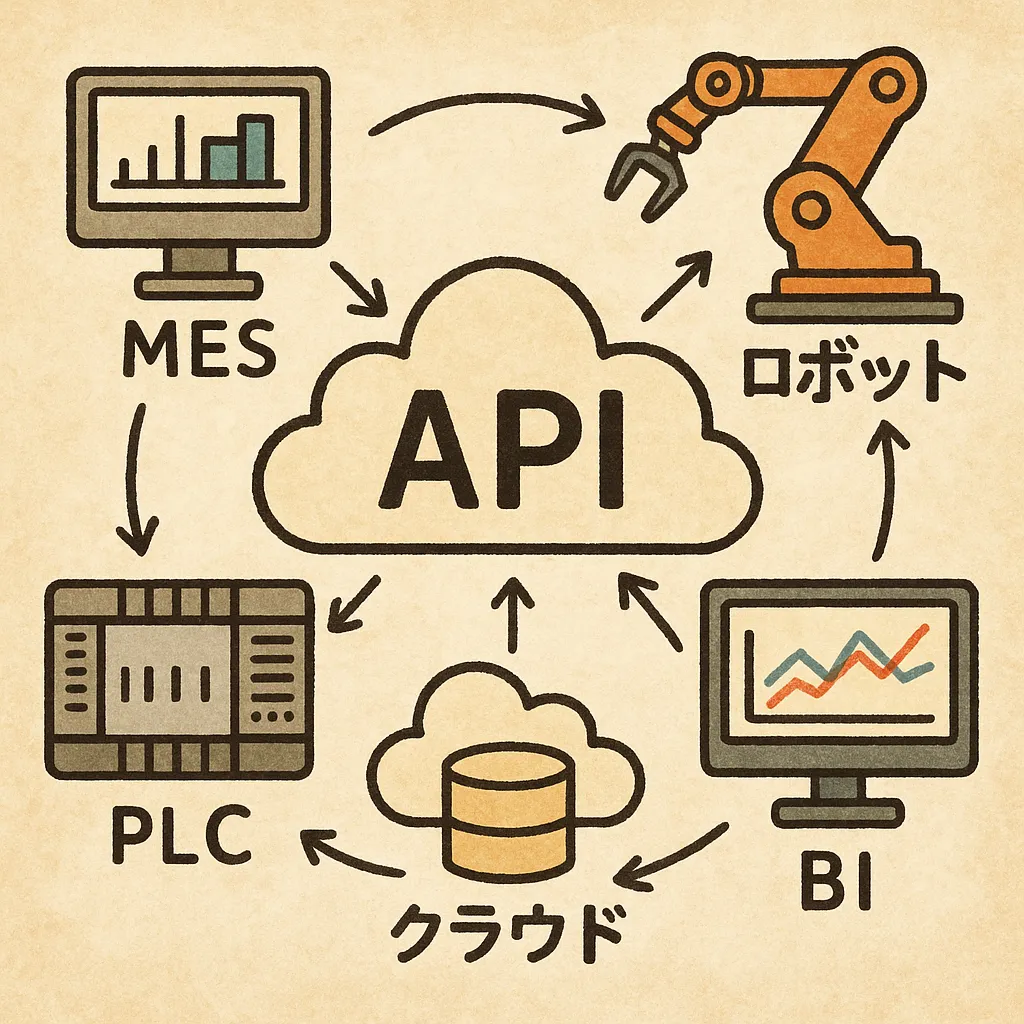工場自動化と聞くと、ロボットやセンサー、PLCなどのハードウェアが注目されがちですが、最近では「API対応」がキーワードとして急浮上しています。
API(Application Programming Interface)は、異なるシステムやアプリケーション同士をつなぐ“共通の言語”のようなもので、現場の機器やソフトウェアを柔軟につなぎ、自動化の範囲を一気に広げる重要な役割を果たします。
APIとは?なぜ自動化に必要なのか
APIとは、ソフトウェア間でデータのやりとりをするための「入り口」です。たとえば、生産実績を記録するシステムと在庫管理システムがAPIでつながっていれば、生産が完了した瞬間に在庫情報が自動で更新されます。
自動化の現場では、以下のような課題があります。
- システムごとに連携ができず、手作業で転記している
- 複数メーカーの設備をまとめて監視できない
- 管理ツールやダッシュボードに反映が遅れる
これらを解決するのが、APIによる“システム間の橋渡し”です。
よくある活用シーン①:MESと他システムの連携
製造実行システム(MES)は、生産指示・進捗管理・実績収集を担う中心的な存在ですが、ERPや在庫管理システムと連携していなければ情報が断絶します。
APIを使えば、
- MESが製品完成を検知 → ERPが出荷準備へ連携
- 品番・ロット・工程情報をリアルタイムで伝達
- 生産遅延時はスケジューラーへ即通知
といった“つながる製造現場”が実現します。
よくある活用シーン②:PLCとクラウドの中継に
APIは「ハードとクラウド」の橋渡しにも使われます。たとえば、PLCの稼働データをエッジデバイスがAPI経由でクラウドへ送信することで、外出先でもリアルタイム監視が可能になります。
さらに、ダッシュボードアプリ(Power BIなど)とAPIを使えば、必要なデータを自動抽出して可視化できます。
よくある活用シーン③:ロボットと管理システムの連携
最近では、ロボット制御システムや自動搬送機(AGV)などにもAPI対応製品が増えています。これにより、
- AGVの位置情報をAPIで取得 → 倉庫管理システムと同期
- 稼働状況をAPI経由で監視し、異常時はSCADAに連携
- ロボットの稼働ログを分析ツールにリアルタイム転送
といった柔軟なシステム設計が可能になります。
API導入のメリット
- データの一元化:複数の設備・ソフトウェアを統合管理
- 手作業の削減:転記・集計・通知作業を自動化
- 柔軟なシステム構築:ベンダーに依存せず、必要な機能を後から追加
- 他部署やクラウドとの連携強化:営業、品質、経営層まで“つながる”情報共有
導入の際の注意点
- APIの仕様確認:REST APIか、SOAPか、など形式に注意
- セキュリティ:通信時は認証や暗号化を徹底(例:OAuth、HTTPS)
- データの整合性:更新頻度や同期ルールを明確に
- メンテナンス性:APIの変更履歴・バージョン管理を怠らない
APIは便利な反面、「設計の曖昧さ」がトラブルの原因にもなり得るため、仕様書の整備やテスト環境の活用が重要です。
まとめ:APIは“現場と経営をつなぐインフラ”
今や、APIはただの技術用語ではなく、製造業の自動化を本質的に加速させる“見えないインフラ”です。
ロボット、PLC、MES、ERP、BI――。
それらがバラバラに動くのではなく、APIで有機的につながることで、はじめて「スマート工場」としての全体最適が実現します。
これからの自動化には、“設備を動かす”だけでなく、“情報をつなげる”視点が不可欠です。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。