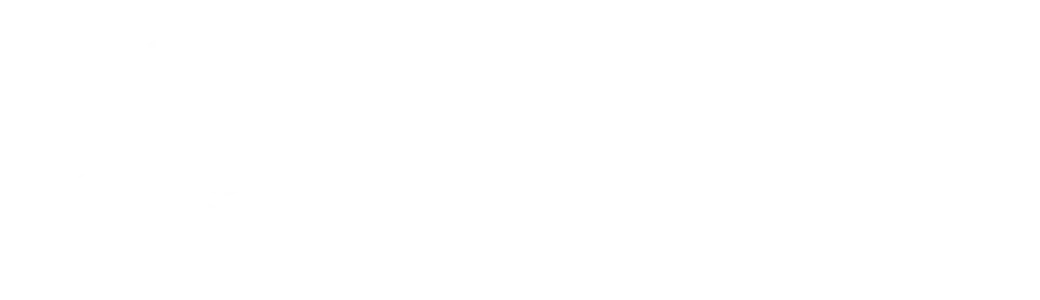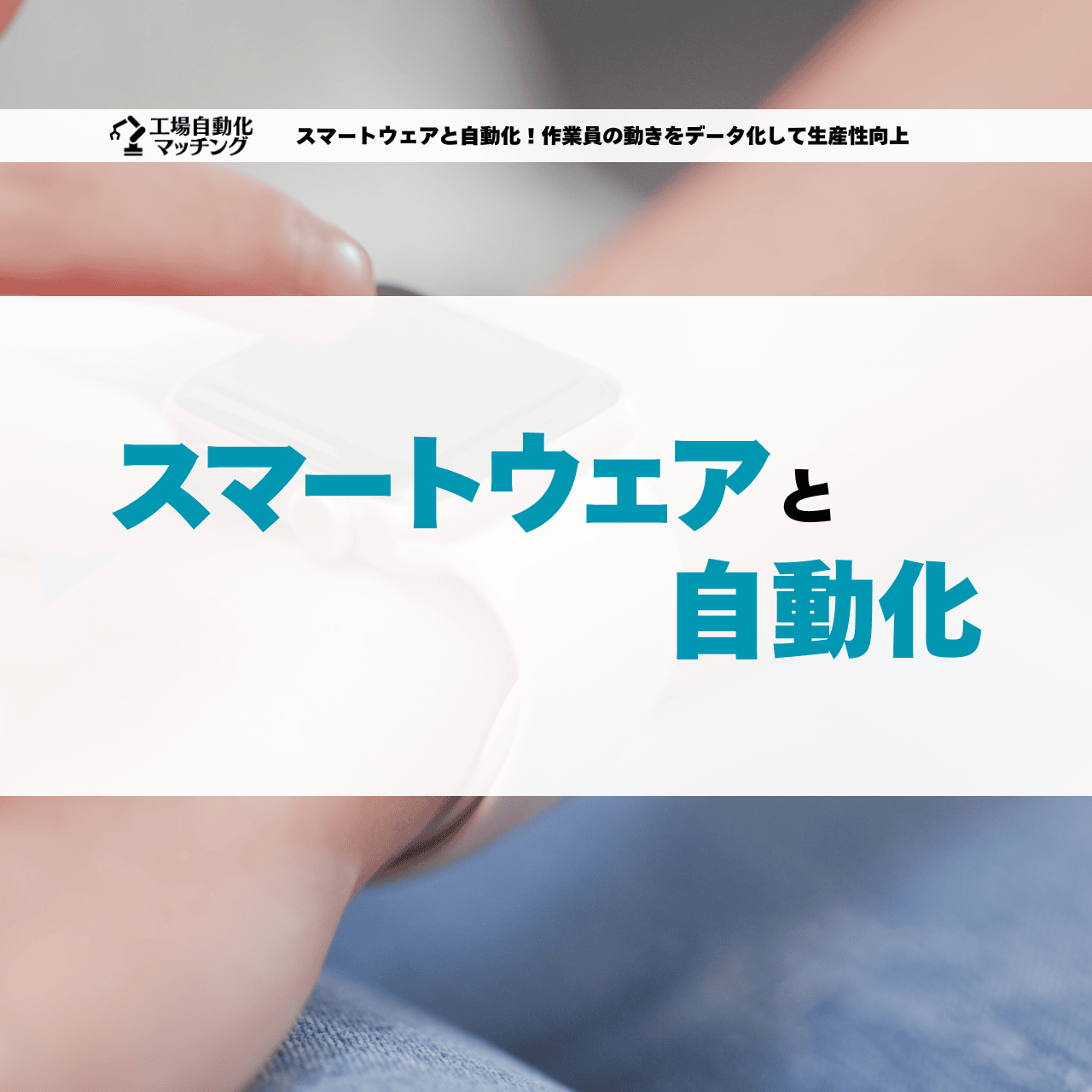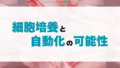製造業や物流現場では、これまで人の作業に頼ってきた工程が多く存在してきました。しかし、近年注目されているのが「スマートウェア」と呼ばれる着るIoT機器です。
スマートウェアを作業員が装着することで、動作や姿勢、位置情報などをリアルタイムで収集・分析でき、作業の無駄を可視化することが可能になります。さらに、自動化技術と組み合わせることで、人と機械の連携効率が大幅に向上し、生産性や安全性の向上につながると期待されています。
この記事では、スマートウェアの概要から、製造現場での活用事例、そして自動化との相乗効果について初心者にも分かりやすく解説します。
スマートウェアとは?
● ウェアラブルデバイスの一種
スマートウェアは、作業着やアンダーウェアにセンサーを内蔵したウェアラブルデバイスです。体の動きや姿勢、心拍数、温度、位置情報などを常時モニタリングできる機能が備わっています。
● 主な搭載センサー
- 加速度センサー(動作の大きさや方向)
- ジャイロセンサー(回転や傾き)
- 心拍センサー(疲労・健康管理)
- GPSやビーコン(位置情報)
これらを使って作業員の状態や動きを“数値化”することが可能です。
スマートウェアがもたらすメリット
1. 作業の無駄を“見える化”して改善
人の動きは感覚や経験に頼る部分が多く、無駄な動線や過剰動作に気づきにくいという課題がありました。スマートウェアを使うことで、作業員一人ひとりの動作パターンを数値化・分析でき、以下のような改善が可能になります。
- 遠回りしていた移動ルートを最適化
- 無駄なしゃがみ・立ち上がり回数を削減
- 効率的な作業手順をモデル化して教育に活用
2. 安全対策と健康管理に役立つ
作業中の無理な姿勢や疲労の蓄積は、事故やけがの原因になります。スマートウェアを活用すれば、異常な動きやバイタルの変化をリアルタイムで検知し、警告を出すことができます。
- 長時間同じ姿勢 → アラートで休憩を促す
- 心拍数の異常 → 管理者が状況を把握
- 転倒の検知 → 即座に応急対応が可能
作業員の安全を守るツールとしても非常に有効です。
3. 人とロボットの連携がスムーズに
スマートウェアによって作業員の位置や動きがリアルタイムで把握できれば、協働ロボットとの干渉を避ける制御が可能になります。
たとえば:
- 作業者が近づいたらロボットが停止
- 一定の距離で並走する搬送ロボット
- 人の動きを予測してタイミングよくパーツ供給
自動化と連動することで、“人と機械がぶつからず、安全に働く”環境が整います。
導入事例紹介
◆ 自動車部品メーカー(中堅企業)
導入目的:作業の標準化とミス削減
施策:主要作業者にスマートウェアを着用させ、効率の良い動きとそうでない動きを比較。
結果:平均作業時間を15%短縮。教育用の動画も作成し、新人教育の質が向上。
◆ 精密加工工場(中小企業)
導入目的:腰痛リスクの軽減と安全管理
施策:ベテラン作業者の腰の曲げ伸ばし頻度を可視化し、作業台の高さや部品配置を改善。
結果:腰痛による離脱者がゼロに。満足度も上昇。
◆ 食品加工業(大手企業)
導入目的:衛生区域での作業モニタリング
施策:作業中の動線を分析し、最短移動ルートを再設計。
結果:1日あたりの移動距離が30%減り、作業効率と衛生管理が同時に改善。
導入の注意点
● 作業員のプライバシー配慮
常にデータを取得されることへの抵抗感が出る可能性があります。データは作業改善のみに使うことを明確にし、個人監視ではないことを丁寧に説明することが大切です。
● 使い勝手や着心地の確認
スマートウェアは機器であると同時に「作業着」でもあります。着用時のストレスやサイズ、洗濯のしやすさなども考慮する必要があります。
● データをどう活かすかの設計が重要
導入しただけでは成果は出ません。取得したデータを分析・可視化・改善までつなげる体制を整えることが、投資対効果を高めるカギです。
今後の展望
今後は、以下のような進化も期待されています。
- AIと連携した自動分析によるリアルタイム改善指示
- ARグラスとの連動による作業ナビゲーション
- クラウドと連携して本社や拠点間で比較・展開
さらに、スマートファクトリーとの融合が進めば、「人の動き」も自動化ラインの一部として組み込まれる未来が見えてきます。
まとめ
スマートウェアは、作業員の動きを数値として“見える化”し、改善につなげる新しいツールです。
これを自動化技術と組み合わせれば、人の能力を最大限に活かしつつ、ロボットや設備との最適な連携が可能になります。
- 作業のムダ削減
- 安全性の向上
- 教育・標準化の効率化
- 人と機械の協働向上
これからの現場改善には、“現場の声”だけでなく“現場の動き”をデータで見ることが重要です。
まずは、小さな範囲からでもスマートウェアを導入し、「見える現場づくり」を始めてみてはいかがでしょうか。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。