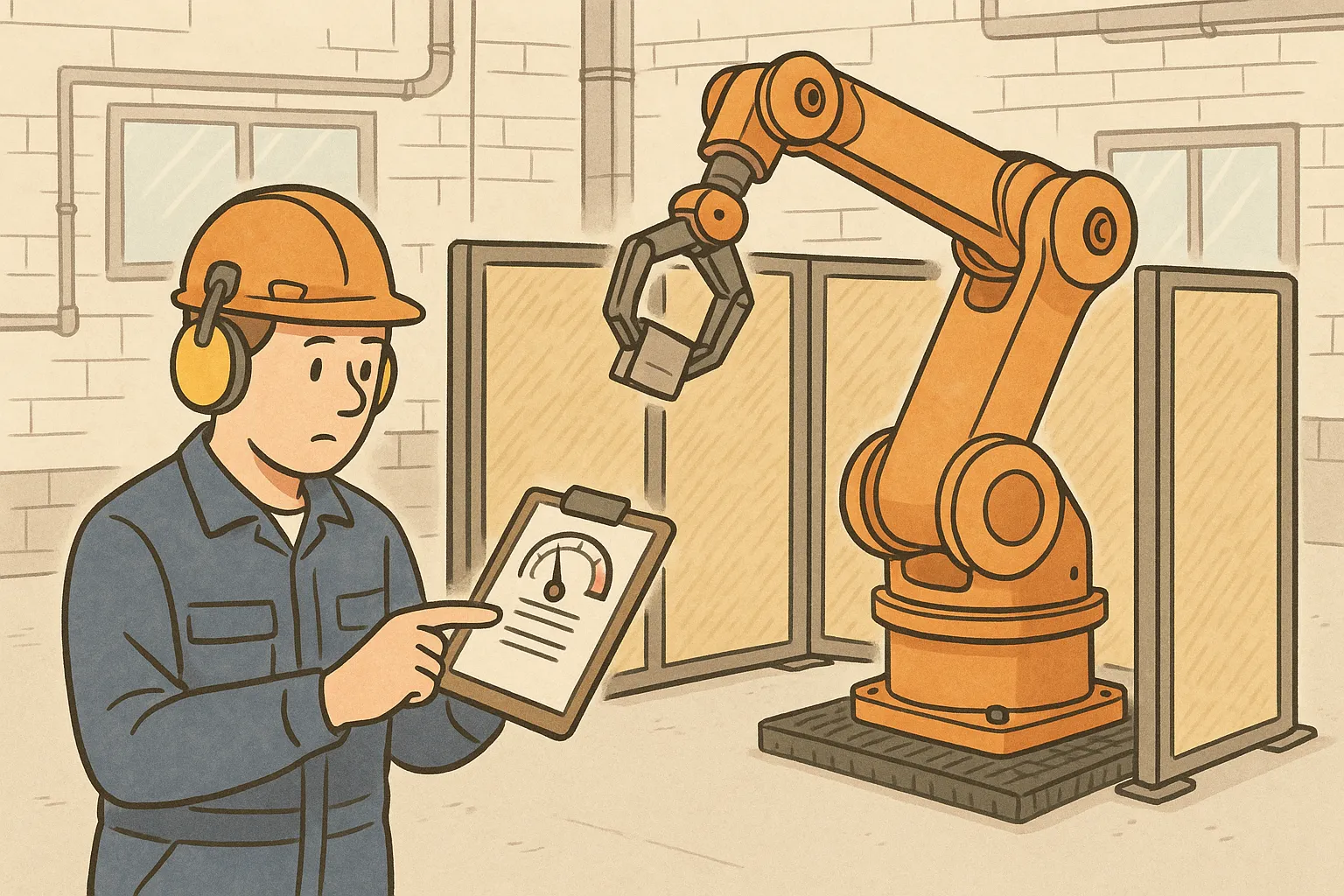製造現場における自動化は、生産性向上や省人化の切り札として広く導入が進んでいます。
しかし、新たな設備やロボットを導入する際に、意外と見落とされがちなのが「騒音」と「振動」の問題です。
これらは作業者の健康や集中力に影響を与えるだけでなく、近隣への騒音トラブルや設備の劣化原因にもなりかねません。
騒音がもたらす現場への影響
工場の騒音は、機械の稼働音、コンベアの振動音、エアの噴出音などが複合的に絡み合って発生します。これらが85dBを超えると、長時間の作業により聴力への影響が懸念されます。
また、大きな音の中では作業員同士の声が通りにくく、指示や警告が伝わらないリスクも高まります。
作業効率や安全性を損なわないためにも、騒音の抑制は重要なテーマです。
振動による設備・人への影響
振動は設備のベースや床材を通じて広がり、近隣の機器や建物にまで影響を及ぼします。機器の微細なズレや摩耗、センサー誤動作の原因にもなりうるため、精密作業を伴う自動化現場では無視できない問題です。
また、長時間振動にさらされた作業者は、筋肉や神経への負担を感じるケースもあります。
配慮ポイント1:防音・吸音対策の導入
自動化設備の導入に際しては、機械本体の防音性だけでなく、周囲の構造物にも吸音材や防音パネルの設置を検討しましょう。特に稼働音が大きい搬送機や加工装置などには、防音カバーの設置が効果的です。
また、作業者の耳元への負担を軽減するため、静音タイプのエアコンポーネントや低騒音型のモーターを選定することも重要です。
配慮ポイント2:防振構造の採用
振動に対しては、設備のアンカーボルト固定や防振ゴムの活用、防振台の設置などが有効です。
特にロボットアームや精密加工機では、細かな振動でも品質に影響するため、床構造を含めた振動対策を設計段階から考慮する必要があります。
既設の床に設置する場合も、レベル調整を正確に行い、床のたわみや共振を防ぎましょう。
配慮ポイント3:定期的な騒音・振動のモニタリング
導入時だけでなく、稼働後も騒音・振動の状態を継続的に把握することが大切です。
デシベル計や振動センサーを活用してデータを収集し、一定の基準を超えた場合はメンテナンスや装置の見直しを行う仕組みを整えることで、長期的に快適で安全な環境を維持できます。
まとめ:静かで安定した現場が自動化を支える
自動化の効果を最大限に引き出すには、作業環境の静音化と安定化が不可欠です。
騒音や振動への配慮は、設備の寿命や作業者の健康にも直結します。
設備導入時には、単に性能だけを見るのではなく、「その機械が現場に与える影響」を全体でとらえ、総合的な改善を進めることが成功への第一歩です。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。