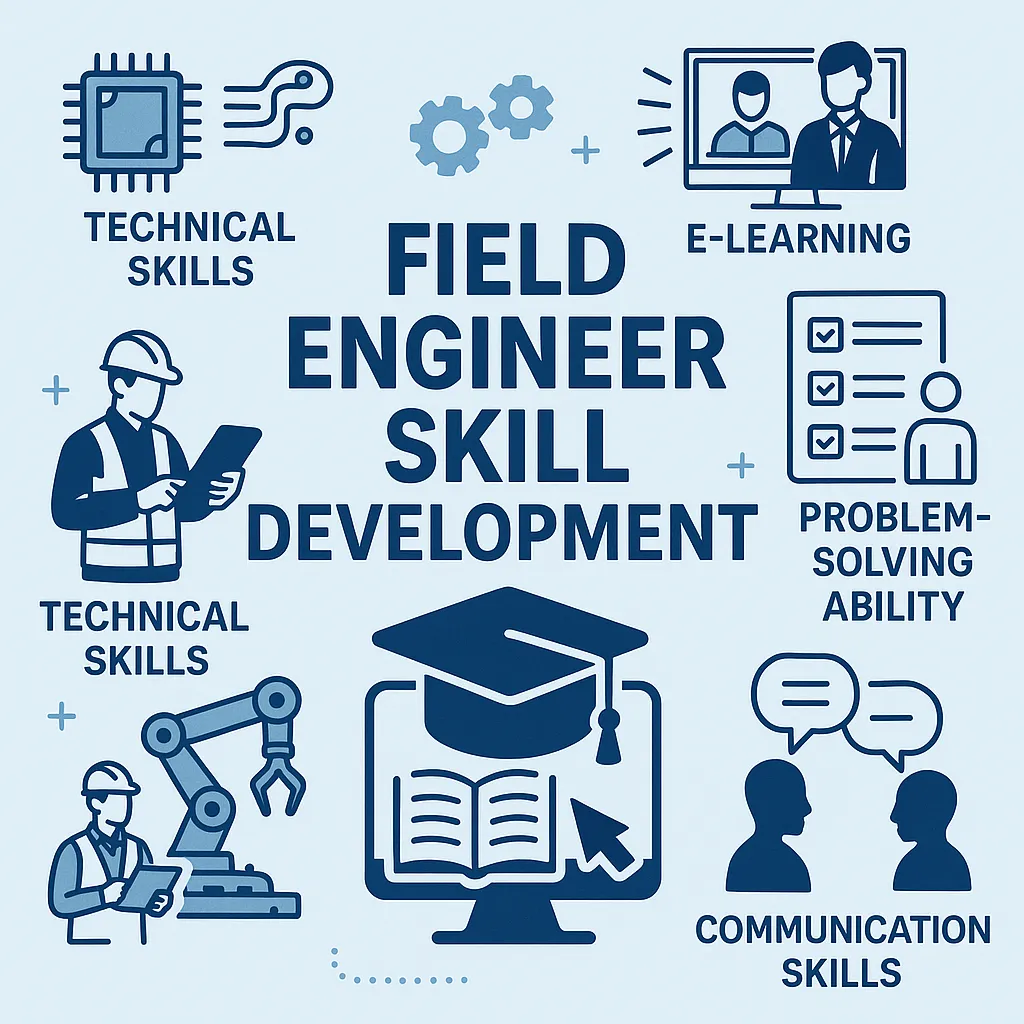製造業や自動化設備の分野で欠かせない存在――それがフィールドエンジニアです。設備の据付や立ち上げ、トラブル対応、定期点検など現場に出向いて対応する彼らは、まさに“現場力”の要です。
しかし近年、設備の高度化や人材不足、技術の世代交代などの背景から、「経験だけに頼らない、体系的なスキルアップ」が求められるようになっています。
本記事では、フィールドエンジニアに必要なスキルとは何か、どのようにして成長支援を行うか、そしてeラーニングを活用した教育手法について、初心者にもわかりやすく解説します。
フィールドエンジニアの主な役割
まずは、フィールドエンジニアの業務を整理してみましょう。
| 業務内容 | 説明 |
|---|---|
| 機械・装置の据付 | 客先の現場に行き、設備を組み立てて稼働状態にする |
| 初期調整・設定 | 制御装置(PLC)、センサー、駆動部などの調整 |
| 保守・点検 | 定期メンテナンスや稼働中の設備の状態確認 |
| トラブル対応 | 故障発生時の復旧対応、原因調査 |
| 顧客対応・報告 | 作業完了後の説明、報告書作成、改善提案など |
こうした業務には、幅広い知識・技術と、現場での臨機応変な判断力が求められます。
求められるスキルの種類
フィールドエンジニアに必要とされるスキルは、次のように分類できます。
技術的スキル(ハード面)
- 電気回路、シーケンス制御(PLC)
- 空圧・油圧機器の知識
- モーターやセンサーなど機器の仕様理解
- 図面やマニュアルの読解力
ソフトスキル(対人・思考面)
- 現場対応力(急な変更・異常にも落ち着いて対応)
- 顧客とのコミュニケーション能力
- 安全意識と危険予知力
- チームとの連携と報告・連絡・相談(ホウレンソウ)
デジタルスキル
- リモートメンテナンスツールの操作
- IoT機器の設定やネットワーク知識
- 報告書作成・データ活用(Excel、PDF、共有ツール)
スキルアップの壁:現場任せに限界
これまで多くのフィールドエンジニアは、「現場で学ぶ=OJT中心」で育成されてきました。
しかし最近では以下のような課題が顕在化しています:
- 教える側のベテランが減少し、技術継承が困難に
- 作業の安全性・効率性の観点から見て覚える教育に限界
- 全国各地に現場があり、一斉教育が難しい
このような背景から、体系的かつ個別に対応できるスキルアップ支援が求められています。
そこで注目される「eラーニング」の活用
eラーニング(オンライン学習)は、場所や時間にとらわれずに学べる教育手法として、フィールドエンジニアの育成にも非常に有効です。
● 主なメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間と場所を選ばない | 出張先でも移動中でも学習可能 |
| 個人のレベルに合わせて学べる | 初級〜上級まで、内容を選べる |
| 繰り返し学習ができる | 苦手分野の復習に最適 |
| 教育の標準化が可能 | 講師の技量に左右されず、全員が同じ知識を習得できる |
実際のeラーニング活用例(現場導入事例)
● ある自動機メーカーの場合
課題:若手エンジニアが多く、PLCやセンサーの基礎知識が不足。現場投入時のミスが発生していた。
対応:
- eラーニング教材(動画・テスト)を導入
- 「設備据付コース」「制御回路基礎」「安全教育」など、レベル別に設計
- 週1回の社内勉強会と併用
効果:
- 短期間で共通理解が進み、現場でのミスが約30%減少
- 教育担当者の負担軽減
- 若手社員から「自分のペースで学べて助かる」との声が増加
eラーニングの導入で意識すべきこと
「現場の実務」とつながる設計にする
例)制御理論だけでなく、「実際にどこで使うのか」を動画で示すと理解度が高まる
学習状況を見える化する
- テスト結果や進捗率を共有することで、学習のモチベーション向上
OJTとの組み合わせが効果的
- eラーニングで学んだ後、実際の装置での体験を通じて定着させる
今後求められる教育の方向性
| 教育方法 | 特徴 |
|---|---|
| eラーニング | 知識の標準化・自学習に最適 |
| OJT | 実機の扱い、応用力の習得 |
| VR/ARトレーニング | 現場再現・危険体験の仮想化 |
| マイクロラーニング | 5分〜10分の短時間学習で記憶に残りやすい |
これらを組み合わせることで、「いつでも・どこでも・自分に合った」学習環境の構築が可能になります。
まとめ
フィールドエンジニアは、製造業の自動化・DX化を支える“最前線の技術者”です。技術の進化とともに、現場で求められるスキルも高度化・多様化しています。
だからこそ、計画的・段階的にスキルアップを支援する仕組みが不可欠です。eラーニングは、そうした取り組みを実現するための有力な手段です。
単なる学習ツールではなく、“人材の成長”を支える仕組みとして、今後さらに活用が進んでいくことでしょう。
個人も企業も、「学び続ける力」を武器に、これからの製造現場を支えていきましょう。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。