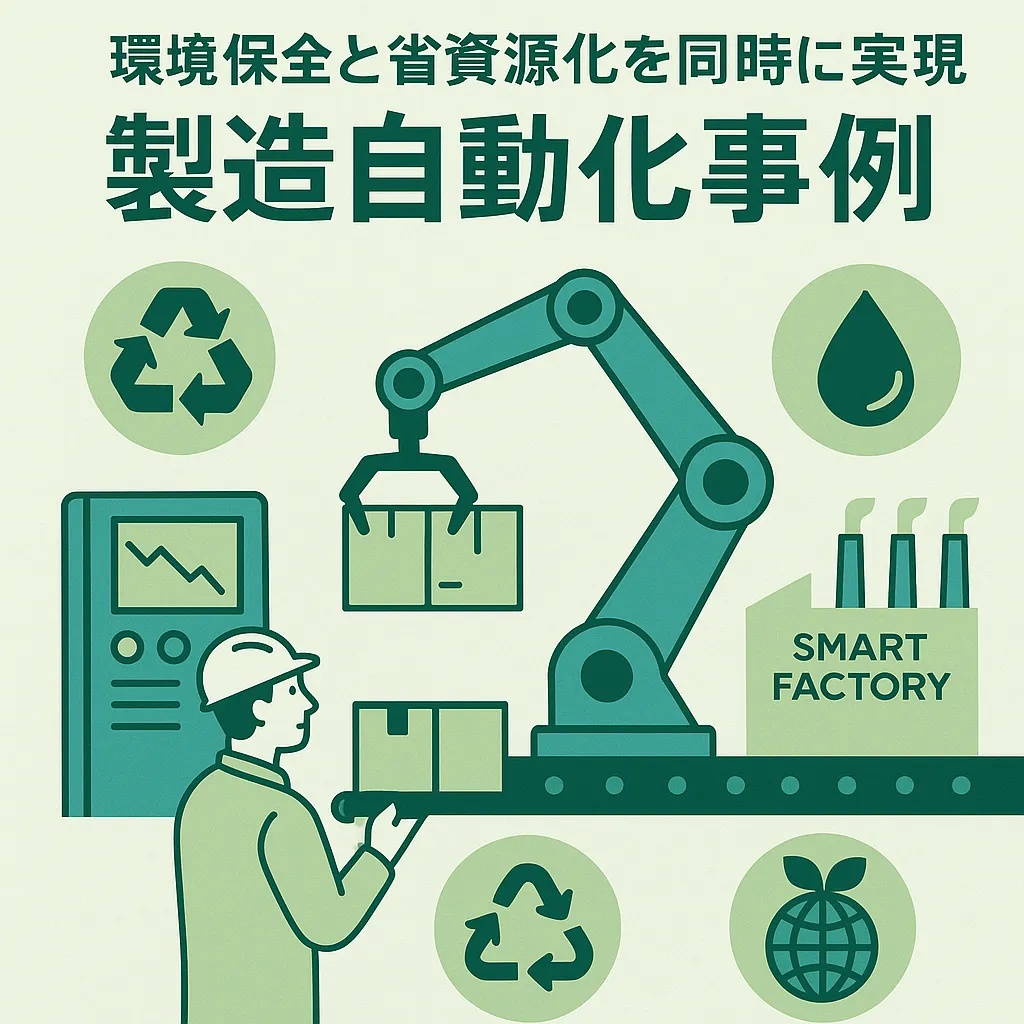地球温暖化、資源枯渇、廃棄物問題──。持続可能な製造業を実現するためには、「環境への配慮」と「限りある資源の有効活用」が不可欠です。
このような背景の中、製造現場では“自動化技術”を活用することで、環境保全と省資源化を同時に実現する取り組みが進められています。
本記事では、初心者の方にも分かりやすく、環境保全と省資源化を両立させた実際の製造自動化事例を紹介しながら、その効果と導入のポイントを解説します。
製造業が抱える環境と資源の課題
製造業では、以下のような課題が環境・資源の観点で指摘されています。
- エネルギー消費の多さ(電力、ガス、燃料など)
- 材料のロスや不良品の発生
- 冷却水や洗浄液などの使用量と廃棄負担
- CO₂排出量の増大による気候変動リスク
これらの課題に対して、省エネ機器の導入や廃棄物削減は従来からの施策ですが、自動化を活用することでさらに高度な省資源・省エネルギーが可能になります。
自動化による環境保全と省資源化のポイント
エネルギー使用の最適化(見える化+制御)
IoTセンサーを使って、設備ごとの電力・エアー・ガス使用量を可視化し、AIや自動制御で無駄を削減できます。
導入例:
- 稼働状況に応じてコンプレッサーや冷却機を自動でON/OFF
- アイドリング時間を制御し、「必要な時だけ動かす」運用に切り替え
- 太陽光や蓄電池との連携制御で再生可能エネルギーを最大活用
材料ロスの最小化とリサイクル工程の自動化
部品の切削、成形、接合などの加工工程で発生する材料ロスや不良品を、画像処理やAI検査によりリアルタイムで判定・修正することで、不要な廃棄を減らすことが可能です。
導入例:
- 溶接不良をその場で検知し、自動補正
- 切削くずを自動回収し、再生ラインへ搬送
- 部材の残量をセンサーで把握し、無駄な発注を抑制
水や薬品の循環利用を自動化
洗浄工程や冷却工程では大量の水や薬品を使いますが、自動化によってろ過・再利用・補充を自動で制御することで、水資源や化学物質の使用量を大幅に削減できます。
導入例:
- 洗浄液の自動ろ過+濃度測定+自動補充制御
- 冷却水を熱交換器で再利用し、連続運転化
- 蒸気の熱を再回収するエネルギー回生システム
実際の製造自動化事例
事例①:電子部品メーカーの空調+照明制御
クリーンルームを持つ電子部品工場では、空調と照明の自動制御システムを導入。
- 工場内の人の位置をセンサーで検知
- 稼働中エリアのみ空調・照明を最適制御
- 年間で15%の電力削減を実現
事例②:プラスチック成形工場での原料ロス削減
自動画像検査と金型温度の自動調整を連携させた成形ラインを構築。
- 成形不良が発生する兆候をAIが検出
- 金型温度や圧力をリアルタイムで補正
- 不良品率が従来の5%から1%以下に低下し、樹脂使用量を削減
事例③:自動車部品工場の切削くずリサイクルライン
アルミ部品の切削加工後、くずを自動回収して圧縮・溶解・再利用するラインを構築。
- 回収と処理をロボットとコンベアで自動化
- 原材料使用量を年間で30トン削減
- 廃棄物処理コストも削減し、CO₂排出量を大幅に抑制
導入のステップとポイント
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 現状分析 | エネルギー・水・材料の使用状況を数値で把握する(見える化) |
| ② 対象工程の選定 | 消費量が多く、無駄が発生しやすい工程から優先的に自動化対象とする |
| ③ 小規模導入→効果検証 | 初期コストを抑えるため、スモールスタートで効果測定 |
| ④ 現場の理解と協力 | 作業者と連携し、自動化が省力化と環境貢献の両方を実現することを周知 |
今後の展望
今後は、AIやクラウド、5Gなどの技術が進化することで、より高精度な省資源・省エネルギー制御が可能になると期待されています。
また、脱炭素経営やESG対応が企業評価に影響する時代となり、環境保全とコスト削減の両立は“攻めの経営戦略”としても重要です。製造業においても、単なる生産効率化ではなく、「持続可能なスマートファクトリー」の構築が今後の鍵を握ります。
まとめ
環境保全と省資源化は、企業の社会的責任であると同時に、コスト削減やリスク低減にもつながる重要なテーマです。
自動化技術を活用することで、無駄を可視化し、削減し、循環させる仕組みを構築することができます。これは、製造現場の未来を支える“両利きの投資”とも言えるでしょう。
環境と経済の両立を目指す第一歩として、自社の製造工程における自動化の可能性を、ぜひ検討してみてください。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。