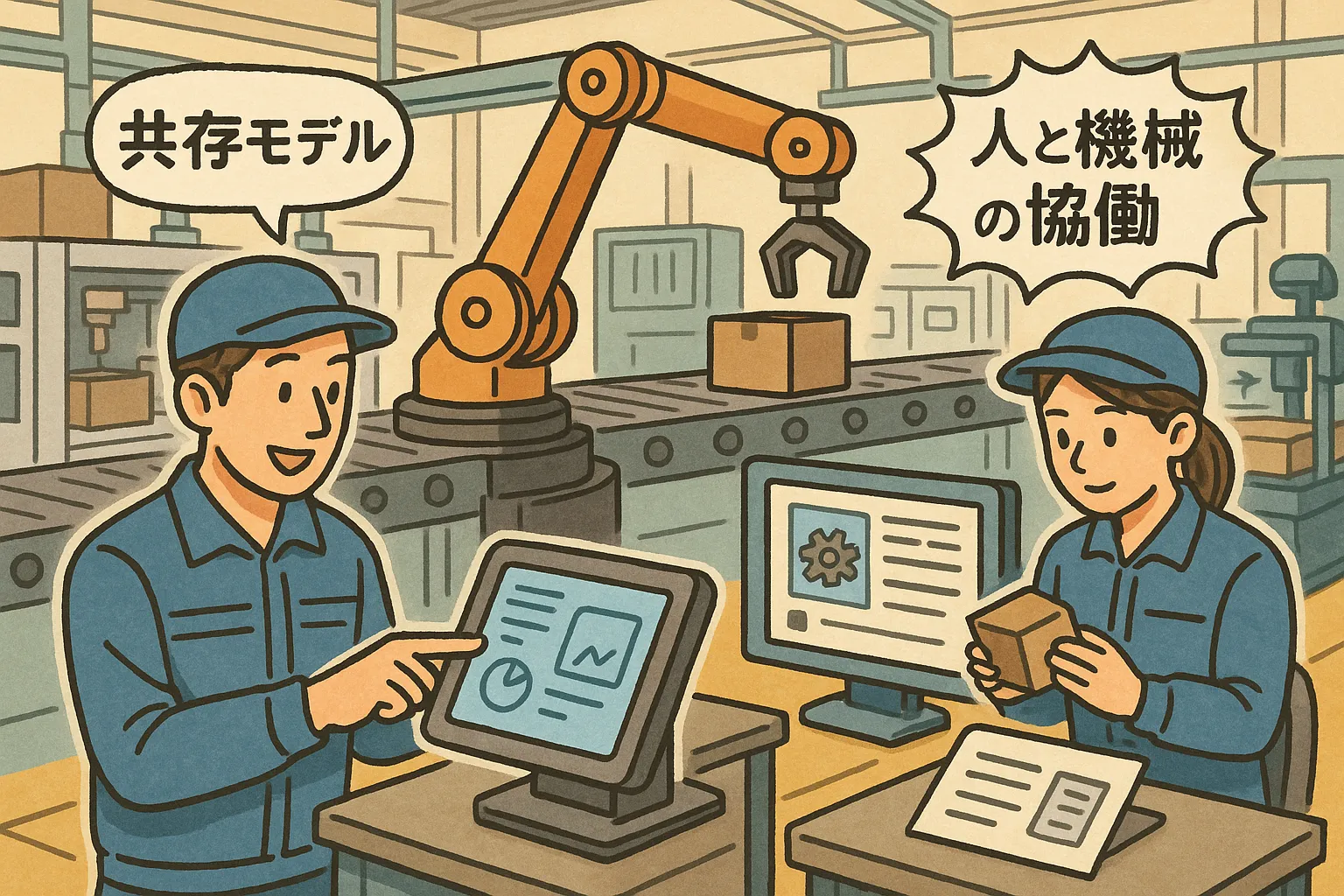「工場の自動化=人の仕事がなくなる」といった誤解が根強くありますが、実際の現場では人と機械の共存によって生産性が高まるケースが増えています。
特に非正規社員(派遣・パート・アルバイトなど)の存在は、製造現場の柔軟な運用に欠かせない存在です。
本記事では、「非正規社員の活用」と「自動化」の共存モデルについて、初心者の方にも分かりやすく解説します。
背景:なぜ“共存”が必要なのか?
現在、多くの工場で以下のような課題が同時に存在しています。
- 人手不足が慢性化
- 人材の定着率が低い
- 作業の属人化と教育負担が大きい
これらの課題に対し、「非正規社員をうまく活用しながら」「人にしかできない部分を補い」「自動化で反復作業を任せる」という“役割分担型の運用モデル”が注目されています。
自動化で置き換えるべき業務
まずは、自動化に適した業務から明確にしていきましょう。
- 反復作業:組立・仕分け・検品など
- 危険・過酷な作業:高温・重労働・有害物質の取り扱い
- 正確さが求められる作業:定量充填・寸法検査
こうした部分は機械やロボットに任せることで、人の負担を軽減し、ヒューマンエラーを削減できます。
非正規社員が担うべき業務
一方、人の判断や柔軟な対応が必要な工程では、非正規社員の力が不可欠です。
- 製品の外観確認(異物・傷などの微細な判断)
- 最終仕上げや簡易修正作業
- 異常検知時の報告・初期対応
- ラインの段取り替え・清掃など
これらは「考える力」「対応力」が求められるため、一定のトレーニングとマニュアル化された支援環境が重要になります。
共存モデルの設計ポイント
① シンプルなUI設計で誰でも使える設備に
- 操作パネルをアイコンと色で分かりやすく
- 異常時は自動で対処手順を表示(マニュアル連動)
- 音声ガイドや多言語対応で教育負担を軽減
② マニュアルとOJTの“標準化”
- 誰が教えても同じ品質になるよう、動画や画像つきの手順書を整備
- ステップバイステップ形式で作業を分解して教育
- 習熟度チェックリストで進捗を管理
③ 機械と人の“協働工程”を可視化
- 例えば「ロボットが並べた部品を人が検査→不良なら戻す」といった連携設計
- デジタルサイネージやランプで作業の開始・終了を明示
- タスクを明確に分けることで混乱や重複を防止
事例紹介:食品工場での成功例
ある中堅食品メーカーでは、非正規社員が6割を占める工場で、ラインの一部自動化を導入しました。
- 袋詰め工程をロボットが担当
- 検品・梱包・ラベル貼りをパート社員が担当
- 各ステップにタブレット型作業ガイドを設置
結果として、
- 教育期間が平均5日→2日に短縮
- 生産効率が15%向上
- 離職率が年間20%→8%に改善
と、非常に高い効果が得られました。
まとめ:人と機械が共に活躍する現場へ
非正規社員と自動化設備は、役割を明確に分けて“共存”させることで、お互いの強みを最大限に活かせるパートナーとなります。
重要なのは、「人に任せる部分」と「自動化すべき部分」を見極めた上で、教育・設計・運用を全体最適で組み立てることです。
自動化が進んでも、人が現場からいなくなるわけではありません。
“人にやさしい自動化”こそが、これからの現場のあるべき姿です。

機械のことで困っている方から状況をヒアリングし、近くの修理業者さんに駆けつけてもらえれば、修理業者同士も助かるし、何より困っている方を早く助けることができる。
そんな思いで機械修理ドットコムを立ち上げました。